用語からはじまる多肉愛
多肉植物の世界に足を踏み入れると、これまで耳にしたことのない専門用語に戸惑うことがあります。
特にイベント会場では、販売者さんが使う言葉が分からず、スムーズな会話ができない…という経験をされた方もいるのではないでしょうか。
周りに他のお客さんがいる中で聞き返すのは勇気がいりますし、結局分からないままになってしまうこともあります。
販売者さんに悪気はなくとも、初心者にとっては専門用語のせいで、多肉植物を楽しむ気持ちが半減してしまうのはもったいないことです。
本記事では、多肉植物にまつわる専門用語をまとめました
.jpg) 筆者
筆者多肉植物の専門店やイベントに出かける前に、ぜひ、目を通してみてください。
多肉植物にまつわる専門用語
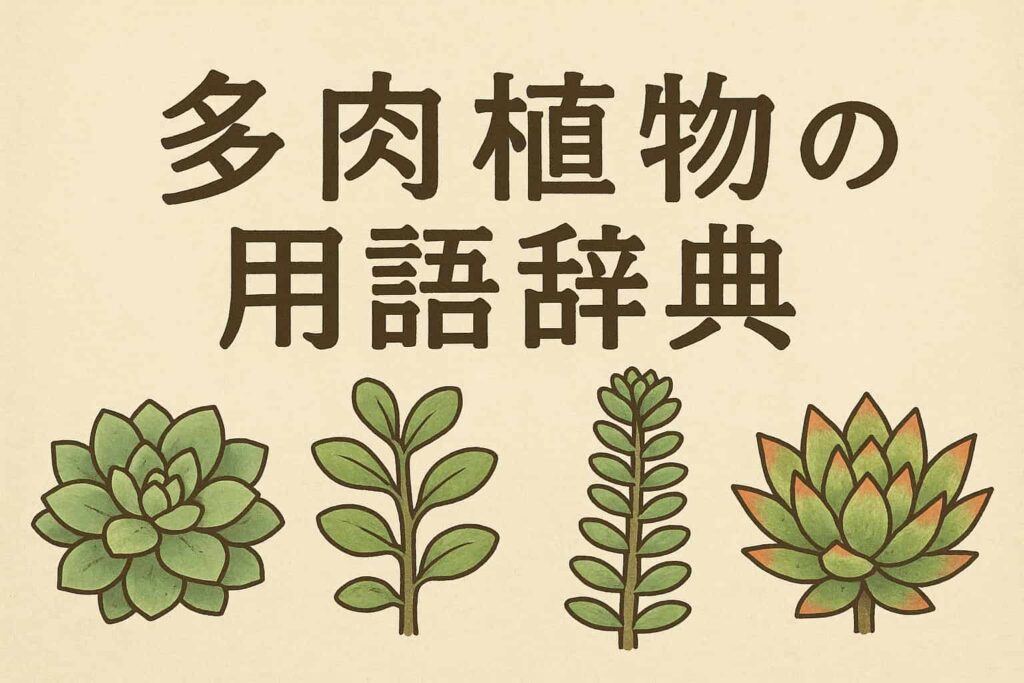
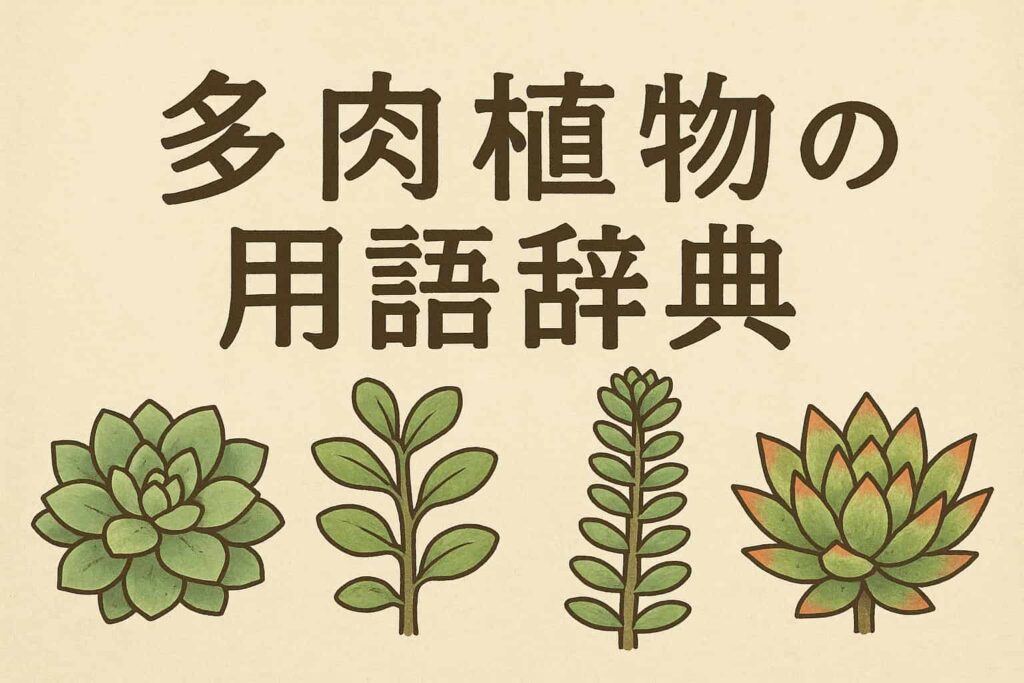
ア行 ~ ナ行
ア行
アレオーレ:サボテン科の特徴として挙げられ、トゲの付け根にある綿毛のような組織のことです。
「刺座(しざ)」と呼ばれることもあります。
アレオーレの有無でサボテン科か、違う植物なのかが区別されています。
たとえば「オベサ」は、サボテンとよく似たすがたをしていますが、アレオーレがなく、トウダイグサ科に分類されている植物です。
イモ:おもに塊根植物(かいこんしょくぶつ)や塊茎植物(かいけいしょくぶつ)が肥大させた、根や茎のことです。
塊根植物などは、肥大させた部分にたくさんの水分を蓄えています。
ウォータースペース:鉢の縁から土の表面まで、意図的に空けておく空間のことです。
このスペースを設けることで、水やりをした際に水が鉢の外にこぼれず、鉢全体にスムーズに行き渡ります。
鉢の縁から2〜3cmほど下まで土を入れることで、鉢内のスペースを有効に活用でき、水やりもスムーズに行えます。
ウォーターマーク:エケベリアや、アガベの葉の表面にあらわれる模様のことです。
ウォーターマークは、ロゼット状に葉が展開する際に、葉の成長速度の差や、重なった葉のトゲが他の葉に触れることで付きます。
A面(エーめん):植物は、見る角度によって印象が変わります。
この角度(面)から見たときが、もっとも魅力的だ。
と感じる植物の面を「A面(エーめん)」と言います。
エケ:エケベリア属の植物の略称のことです。
sp.(エスピー):sp.とは「species」(種)の略語です。
品種名がハッキリと分からない植物に使われます。
「札落ち(ふだおち)」とも似た意味ですが、以下のような違いがあります。
- sp
- 最初から品種名が分からない植物
- 札落ち
- もともと分かっていた品種名が、名札をなくしたことで分からなくなった植物
枝挿し (えださし) :多肉植物の「枝挿し」は、株を増やすための園芸手法です。
去年または今年に生えた枝を切り取り、それを土に植えて、発根させることで新たな個体を増やせます。
挿し木のうち、特に若い枝を使うのが「枝挿し」です。
エッジ:多肉植物の葉の縁や先端部分のことです。
たとえば、紅葉する時期になるとエケベリアの葉先が赤く染まりますが、これは「エッジが色づく」と表現されます。
おもに、エケベリアやグラプトペタルム、グラプトベリアに使われる言葉です。
園芸品種:見た目が特に魅力的なように品種改良された植物のことです。
「栽培品種」も品種改良された植物を意味しますが、以下のような違いがあります。
- 園芸品種
- きれいな花やユニークな葉っぱなど、観賞用の植物を対象とした言葉
- 栽培品種
- 病害虫に強かったり成長が早かったりするなど、収穫量やおいしさに優れた野菜や果樹に使われる言葉
雄株(おかぶ):花粉を作り出す、オス(♂)の性質を持つ植物を指します。
種子をつくるためには、雄株が出した花粉が、メス(♀)の性質を持つ「雌株(めかぶ)」に受粉される必要があります。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
読み方は、「おすかぶ」ではなく「おかぶ」です。
置き肥(おきひ、おきごえ):土に混ぜるのではなく、土の表面に置いて使うタイプの肥料です。
水やりをするたびに少しずつ成分が溶け出し、ゆっくりと植物に吸収されます。
即効性はないものの、数か月にわたって肥料効果が持続するのが特徴です。
雄花(おばな):雄しべだけがあって、雌しべがないか、発達しない花のことです。
雄花がつくる花粉が、メスの「雌花(めばな)」に運ばれることで受粉が成立し、果実や種子が実ります。
(対義語・反対語:雌花(めばな))
親株(おやかぶ):植物の親にあたる個体のことです。
同じ品種でも、遺伝子の違いによって見た目に差が出ることがあります。
植物を選ぶ際には、その親である「親株」を見ることで、成長したときのすがたをある程度知ることができます。
親と子は同じ遺伝子をもつため、同じ環境で育てれば、親株と同じように成長させることが可能です。
(対義語・反対語:子株(こかぶ))
オルトラン:土に混ぜて使う浸透移行性の殺虫剤です。
「オルトラン」は、植物が根から有効成分を吸収し、その植物を食べた害虫に効果があらわれます。
植物が成分を吸収するまでには時間がかかるため、すでに発生している害虫への即効性はありません。
速やかに害虫を駆除したい場合は、スプレータイプの殺虫剤を併用することをおすすめします。
「オルトラン」を土に混ぜておくことで、害虫による被害を早期に抑えられるため、多肉植物愛好家こと“タニラー”には欠かせないガーデニング用品です。
カ行
塊茎植物(かいけいしょくぶつ):乾燥した地域に自生する植物です。
たくさんの水分を蓄えるために、「茎」がユニークな形状に太く進化しました。
過湿に弱いため、頻繁な水やりは必要ありません。
水の与えすぎは根腐れの原因となるため、乾燥気味に育てるのがコツです。
塊根植物(かいこんしょくぶつ):塊茎植物と同じく乾燥した地域に自生しているため、水やりは控えめにします。
塊茎植物と異なる点は、肥大させた部分が茎ではなく「根」という点です。
塊茎植物と明確に区別されないことも多く、まとめて「塊根植物」として流通していることがほとんどです。
カキ仔(かきこ) :親株の根元や幹から出てきた子株を、切り離した株のことです。
もし切り離した時点で、根が出ていれば、他の植物と同様に土に植えて育てられます。
ただし根がない場合は、発根剤を使ったり、水耕で管理したりして、まずは根を生やす必要があります。
親株から「かきとる」ようにして分けることが、「カキ仔」の由来です。
花茎(かけい):葉を付けずに花だけを付ける、開花専用の茎です。
多肉植物は、他の植物よりも花茎が長い品種が多い点も特徴のひとつです。
カット苗(かっとなえ):根や茎を切り落とし、挿し木用に仕立てられた苗のことを指します。
おもに、エケベリアやグラプトペタルム、グラプトベリアに使われる言葉です。
活着(かっちゃく):植物の根がしっかりと土に張り、安定して育つ状態になることを指します。
発根したばかりの「チョロ根」や「微発根」とは異なり、順調に成長できる状態です。
海外から輸入された根のない株が、しっかりと根を張ったものは「活着株」として販売されることもあります。
株分け(かぶわけ):あたらしく子株が出てきたときに、親株と子株を分けて、独立した株として育てる方法です。
植物の数を増やしたいときや、鉢の中が窮屈になってきたときに行います。
カルス:植物を切ったあとにできる、不定形の細胞の塊のことです。
「カルス」は、傷口を保護するだけでなく、あたらしい根や芽を出すための土台となる重要な役割もあります。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
人間の「かさぶた」のようなものと捉えると、分かりやすいでしょう。
寒冷紗(かんれいしゃ):網目状に織られた薄い布で、植物を保護するために使われます。
見た目がよく似たガーデニング用品「不織布(ふしょくふ)」との違いは、以下のとおりです。
- 寒冷紗
- 網目があるため、遮光性だけでなく通気性も高い
- 不織布
- 網目がないため、保温性や防虫性に優れている
.jpg)
.jpg)
.jpg)
用途にあわせて、使い分けたいアイテムです。
気根(きこん):植物の茎や幹から、土に埋まらない状態で生えてくる根のことです。
「気根」は以下のように、さまざまな役割を果たします。
- 空気中の水分を吸収する
- 地面まで伸ばし、植物自身の体重を支える
- 周囲の植物や壁に絡みつき、体を固定する
季節斑・季節錦:特定の季節だけあらわれる、模様(斑)のことを意味します。
温度差などによって、季節の移り変わりを感じ取った植物が、葉の一部を染めます。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
季節斑(季節錦)が鮮明にあらわれるのは、植物の調子がよいタイミングが多いです。
黄中斑(きなかふ):葉の中心部分だけに、黄色い模様(斑)が入っている状態を指します。
ギムノ:サボテン科の「ギムノカリキウム属」の略称です。
黄覆輪(きぶくりん):葉の縁の部分だけに、黄色い模様(斑)が入っている状態を指します。
(同義語:金覆輪(きんぷくりん))
基本用土:「赤玉土」や「鹿沼土」、「ひゅうが土」など、多肉植物の土作りの「ベース」となる土です。
おもに、他の用土と混ぜ合わせて使用するのが一般的です。
複数の基本用土を配合することで、植物に合ったオリジナルの培養土をつくることができます。
基本用土だけでも育てられますが、複数の種類を混ぜ合わせることで、排水性や保水性などのバランスがよくなり、多肉植物をより元気に育てることができます。
強健種(きょうけんしゅ):厳しい環境にも耐えられる丈夫な品種のことです。
夏の暑さや冬の寒さ、水やりを少しばかり忘れても枯れにくいため、はじめて多肉植物を育てる方でもチャレンジしやすい品種です。
共生植物(きょうせいしょくぶつ):お互いによい影響を与え合う、相性のよい植物の組み合わせのことです。
近くで一緒に育てることで、病害虫を防いだり、生育を助けたりする効果が期待できます。
(同義語:コンパニオンプランツ)
休眠期(きゅうみんき):植物の成長が一時的に停滞する期間のことです。
たとえば、夏に元気に育つ多肉植物が、秋に葉を落とし、冬にはほとんど変化が見られなくなった場合、冬が休眠期にあたります。
- 暑い季節が好きな‟夏型”の植物の場合
- 休眠期は「冬」
- すずしい季節が好きな‟冬型”の植物の場合
- 休眠期は「夏」
休眠中の植物は、葉を落としたり、成長点が動かなくなったりするため、枯れてしまったように見えるかもしれません。
しかし実際には、次の成長期に備えて体力を温存している状態であり、枯れているわけではありません。
兄弟株(きょうだいかぶ):同じ親株から採れた種子を蒔いて、育てた植物同士のことです。
親株と完全に同じ遺伝子をもつ「子株」とは異なり、遺伝的な多様性があるため、見た目に違いがあらわれやすいです。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
将来成長するすがたが分からない分、株ごとの個体差を楽しめます。
鋸歯(きょし):鋸(のこぎり)という漢字のとおり、ギザギザしている葉の縁の部分のことです。
一般的に、アガベやディッキアなどの多肉植物に使われる言葉です。
切り戻し(きりもどし):多肉植物の枝や茎を、短く切ることを意味します。
おもに徒長した株を仕立て直したり、大きく成長しすぎた株を、コンパクトに戻したりするときに行います。
- 元の株
- 切った部分のすぐ下からあたらしい芽を出し、再び成長をはじめる
- 切り取った上の部分
- 挿し穂(さしほ)として根を出させることで、あたらしい株として育てられる
グラプトベリア(Graptoveria):グラプトペタルム(Graptopetalum)とエケベリア(Echeveria)の交配種のことです。
見た目が似ているため、グラプトベリア属の植物が、エケベリアとして流通していることもあります。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
比較的安価で手に入りやすく、100円ショップでも見かけることがあります。
群生(ぐんせい):同じ植物が、たくさん集まって育っている状態のことです。
親株の周りに子株がたくさん増えて、ひとつの株のように見える株を「群生株」と呼びます。
化粧石(けしょういし):植物を植えた鉢の土の表面に、装飾のために敷く石のことです。
おもに観賞用として使われますが、以下の役割もあります。
- 土が乾燥しすぎるのを防ぐ
- 水やりの際に、土がはねないようにする
- 土に害虫の侵入するのを防止する
(同義語:化粧砂(けしょうずな))
嫌光性種子(けんこうせいしゅし):発芽に光を必要としない植物の種子のことです。
(対義語・反対語: 好光性種子)
現地球(げんちきゅう):海外から輸入された植物のことです。
(同義語:現地株(げんちかぶ))
(対義語・反対語:実生株(みしょうかぶ))
現地発根株(げんちはっこんかぶ):未発根の株を輸入する場合に、現地(自生国)の畑でいちど発根させてから輸入された植物のことです。
現地で発根させている分、日本に輸入されてから発根しやすい特徴があります。
(対義語・反対語:山採り株)
原種(げんしゅ):品種改良が行われる前の、もともとの野生の状態の植物を意味します。
さまざまな園芸品種や栽培品種の元となった、いわば植物の「祖先」にあたる品種です。
高温障害(こうおんしょうがい):高温多湿の環境で植物に起きる、生理的なトラブルのひとつです。
地球温暖化が進む現代では、高温障害が多くの植物で起こりやすくなっています。
好光性種子(こうこうせいしゅし):発芽に光を必要とする植物の種子のことです。
(対義語・反対語: 嫌光性種子)
交雑種(こうざつしゅ) :異なる品種の植物が交配し、生まれた品種のことです。
- 自然交雑種
- 鳥や虫、風などによって自然に交配した交雑種
- 人工交雑種
- 異なる品種の植物を、人為的に交配させた交雑種
高山植物(こうざんしょくぶつ):標高の高い山に自生する植物のことです。
標高が高い場所は、平地と比べて風や光量(紫外線)が強く、気温が低くなります。
高山植物は葉を小さくしたり、背丈を低くしたりと、高山の特徴にあわせて独自の進化を遂げています。
交配種(こうはいしゅ):性質の異なる品種を交配させて生まれた、あたらしい植物のことです。
子株(こかぶ):親株からあたらしく発生した小さな株のことです。
成長すると、親株から分けることで、単独の個体として育てられます。
(⇔親株)
枯死(こし):完全に植物が枯れてしまうことです。
腰水(こしみず):水を溜めた容器に、鉢ごと浸けている状態のことを指します。
種蒔きや、長期間水を与えるのがむずかしい場合に、採用される給水方法です。
水も劣化するため、定期的に(3~4日ごと)入れ替えるのが望ましいです。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
腰水で使用する水を毎日入れ替えても、根が呼吸できなければ、根腐れを起こすリスクはあります。
仔吹き(こふき):植物の幹や根元などから、あたらしい子株が次々と生えてくる特徴を指します。
サボテンや、丸い形状のユーフォルビアによく見られる現象です。
コーデックス(Caudex):水を蓄えるために、根や茎が太くユニークな形状に発達した植物の総称です。
おもに、塊根植物と塊茎植物をまとめて指す言葉として使われます。
「コーデックス」の定義はあいまいなため、「塊根植物・塊茎植物・アガベ」の総称として使われることもあります。
コンパニオンプランツ:お互いによい影響を与え合う、相性のよい植物の組み合わせのことです。
お互いによい影響がある場合だけでなく、片方の植物にだけよい効果がある組み合わせもあります。
ちなみに、「コンパニオン」は「仲間」を意味します。
(同義語:共生植物)
サ行
CITES(さいてす):絶滅のおそれのある動植物を保護するために、国際的な取引を規制している条約のことです。
正式名称は「Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora」で、頭文字をとってCITES(さいてす)と呼ばれています。
栽培品種(さいばいひんしゅ):病害虫に強かったり成長が早かったりするなど、収穫を目的に品種改良された植物のことです。
園芸として楽しまれる植物ではなく、野菜や果樹などに使われる言葉です。
(類義語:園芸品種)
挿し木(さしき):剪定した(切り落とした)植物の枝から根を出させ、あたらしく植物を増やす方法です。
元の植物と同じ遺伝子をもった「クローン植物」をつくれるのが、挿し木の特徴です。
斜めに剪定することで断面が大きくなり、水を吸い上げやすくなるため、挿し木の成功率を上げることができます。
剪定した傷口から、雑菌が侵入するのを防ぐために、挿し木株の管理には無菌の土を使うことが望まれます。
挿し穂(さしほ):挿し木をするために親株から切り取った、植物の枝や茎のことです。
挿し芽(さしめ):草花を増やす方法のひとつで、茎や葉を切り取って土に挿し、根を出させてあたらしい株を育てることです。
- 挿し芽:おもに草花を対象としている
- 挿し木:おもに木(樹木)を対象としている
刺座(しざ):サボテン科には必ずある組織で、刺の付け根にある綿毛のような組織のことです。
(同義語:アレオーレ)
下葉(したば):幹や株の下の方に生えている葉のことです。
古くなった下葉は汚れや傷が蓄積し、光合成の能力にも支障をきたすため、やがて自然に枯れていきます。
定期的に1〜2枚ほど下葉が枯れ落ちるのは、植物にとってごく自然なことです。
締める(しめる):葉同士の間隔が狭く、全体的にギュッと詰まったすがたに育て上げることを意味します。
特に、葉をロゼット状に展開させる「アガベ」や「エケベリア」などに使われる言葉です。
一般的に、締まった植物に育てるためには、以下のような環境で育てることが重要です。
- 日によく当てる
- 水やり&肥料は控えめにする
- 風通しをよくする
- 鉢を大きくしすぎない
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ただし真夏の直射日光は強すぎるため、光量を調整した方がよいでしょう。
遮光(しゃこう):直射日光を遮ることです。
植物は品種によって好む光量が異なるため、強すぎる光から植物を守り、適切な光量に調整するために行います。
なお、遮光率の考え方は以下の通りです。
- 遮光率が高い=遮られる光量が多い=植物に当たる光は弱くなる
- 遮光率が低い=遮られる光量が少ない=植物に当たる光は強めになる
雌雄異株(しゆういかぶ):雄の花を付ける株と雌の花を付ける株が、別々に存在する植物のことです。
ひとつの株だけでは受粉して、種をつくることができません。
遺伝子を混ぜ合わせることで、環境の変化などに強い子孫を残そうとする、植物の生存戦略のひとつです。
(同義語:雌雄別株)
雌雄同株(しゆうどうしゅ):ひとつの株が、雄花と雌花の両方を咲かせる植物のことです。
ひとつの花の中に雄しべと雌しべを持つ植物には、この言葉は使いません。
(=雌雄同体(しゆうどうたい))
雌雄別株(しゆうべっしゅ):雄の花を付ける株と雌の花を付ける株が、別々に存在する植物のことです。
(同義語:雌雄異株)
純血種(じゅんけつしゅ):他の品種の血が混ざっていない植物のことです。
(⇔交配種)
食害(しょくがい):鳥や虫などに、植物を食べられてしまうことを意味します。
葉に穴が開いたり、形が変わったりするなど、見た目の被害だけでなく、食べられた箇所から雑菌が侵入するなど、生育面でも被害を及ぼすことがあります。
白中斑 (しろなかふ):葉の中心部分だけに、白い模様(斑)が入っている状態です。
白肌 (しろはだ) :葉や茎が白っぽい色をした植物を指す言葉です。
この白さは、品種固有の色である場合もありますが、多くの場合は、強い日差しや紫外線から身を守るために、葉や茎の表面に白い粉をまとうことで生じます。
この白い粉が光を和らげ、植物の体温上昇を抑える役割を果たします。
白覆輪 (しろふくりん):葉の縁の部分だけに、白い模様(斑)が入っている状態のことです。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
「しらふくりん」「しろぶくりん」「はくふくりん」とも言われます。
地植え (じうえ) :地面に、直接植物を植えることを意味します。
鉢やプランターに植える「鉢植え」と比較し、根を張るスペースが広いため、植物の成長速度が早いのが「地植え」の特徴です。
植物を早く成長させたいときや、迫力のあるすがたを楽しみたいときに用いられる手法です。
自家受粉(じかじゅふん):同じ株が咲かせる花同士が、受粉することを意味します。
自家受粉ができる植物は種子をつくりやすいものの、異なる遺伝子が混ざらないため、環境の変化に強い子孫が生まれにくい傾向があります。
(対義語・反対語:他家受粉)
自家結実 (じかけつじつ) :ひとつの植物が自分の花粉で受粉し、実を付けることです。
他の株の花粉がなくても、実を収穫できるのが特徴です。
ジュレる:多肉植物が雑菌に侵され、葉の内部が溶けてゼリー状になることを指します。
葉が半透明に変色し、ひどい場合は枯れてしまいます。
おもに「エケベリア」などに使われる言葉で、特に湿気が多い時期に起こりやすい現象です。
芯止め(しんどめ):植物のもっとも高い位置にある成長点を、切り取ることです。
芯止めを行うと、植物の枝や幹がそれ以上伸びなくなるため、植物の樹高を抑える目的で行われます。
スパイン:おもに「アガベ」に使われる言葉で、葉先や縁に付けるトゲ(鋸歯)のことです。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
「スピン」と呼ばれることもあります。
成長点(せいちょうてん):植物の先端部分などにある、新しい葉や茎、根がつくられる場所のことです。
成長点では活発に細胞分裂が行われており、植物の成長を担っています。
もし成長点がつぶれると、植物はそれ以上伸びることができなくなるため、代わりにあたらしい子株を出すことがあります。
植物のこの性質を利用し、あえて成長点をつぶし、植物を増やすのが「胴切り」などの園芸手法です。
石化 (せっか):植物の成長点が乱れ、平らな帯状になることを指します。
植物の奇形の一種として知られています。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
石化を起こした植物は、独特な見た目になるため、高額な価格帯で取り引きされることが多いです。
施肥(せひ):植物に肥料を与えることを指します。
剪定(せんてい):植物の枝や葉を切る作業のことです。
- 大きさや見た目を整える
- 風通しをよくして病害虫を防ぐ
- 開花を促す
植物の枝葉を剪定すると、それまで枝に届けられていた養分が幹に留まることになり、幹が肥大しやすくなる効果も期待できます。
先祖返り (せんぞがえり) :品種改良などによって得られた特性が消え、もともとのすがたや性質に戻ってしまうことです。
たとえば斑入りの植物が、成長するにつれて斑がなくなり、普通の緑色の葉に戻る現象が先祖返りにあたります。


タ行
耐寒性(たいかんせい):植物が、どれくらいの寒さに耐えられるかを示す言葉です。
- 耐寒性がある植物
- 寒い場所でも調子を崩しにくい
- 耐寒性が高い、または耐寒性が強いとも表現する
- 耐寒性がない植物
- 寒さに弱い
- 耐寒性が低い、または耐寒性が弱いとも表現する
台木(だいぎ):成長速度の遅い植物を、成長速度の早い植物に接ぎ合わせる「接ぎ木」をするときに、その土台となる植物のことです。
「台木」には、病気にかかりにくく、生命力が強い品種が選ばれます。
この「台木」を使うことで、成長の遅い植物も、「台木」から送られる栄養によって早く大きく育つことができるようになります。
耐暑性(たいしょせい):植物が、どれくらいの暑さに耐えられるかを示す言葉です。
- 耐暑性がある植物
- 暑い場所でも調子を崩しにくい
- 耐暑性が高い、または耐暑性が強いとも表現する
- 耐暑性がない植物
- 暑さに弱い
- 耐暑性が低い、または耐暑性が弱いとも表現する
他家受粉(たかじゅふん):別の株から運ばれてきた花粉で、植物が受粉することです。
自分の花粉だけで受粉する自家受粉と比べると、種子をつくるためのハードルが上がります。
ただし複数の遺伝子が組み合わさるため、より環境の変化に強く、あたらしい特性を持った丈夫な子孫が生まれやすくなります。
(対義語・反対語:自家受粉)
タコ物(たこもの):タコの足のように、複数の枝を生やすユーフォルビア属の植物のことです。
縦割り(たてわり):アガベなどの植物を増やす方法のひとつで、株を縦に切り、成長点をつぶすことです。
成長点がつぶれたアガベから、子株が次々と出てくるようになります。
多頭株 (たとうかぶ) :ひとつの株の成長点が複数になり、それぞれの頭が独立した状態の植物のことです。
通常は成長点がひとつしかない品種の植物が、株元から複数の子株が分岐したり、成長点が複数に分かれたりして、独特のすがたになります。
タニパト(多肉パトロール):育てている多肉植物の見回って、状態を観察することです。
たくさんの多肉植物を育てている人が、ひとつひとつに異常がないかを確認する際によく使われる言葉です。
タニラー:「多肉植物を愛する人」という意味の造語で、多肉植物に深い愛情を注ぎ、熱心に栽培しているひとのことを指します。
短葉(たんば):同じ品種の植物と比べて、葉が短い特徴を持つことを指します。
団粒構造(だんりゅうこうぞう):土の粒が小さな塊になり、集まっている状態のことです。
粒と粒の間に適度な隙間ができるため、水はけや風通しがよくなります。
ドロドロになった土とは反対の状態であり、植物が元気に育つためには、この団粒構造が土の中に形成されていることが大切です。
.jpg)
.jpg)
長日植物(ちょうじつしょくぶつ):昼の時間(日照時間)が長くなると開花する植物のことです。
ちょろ根(ちょろね):それまで根がなかった植物に、あたらしく生えてきたばかりの短い根のことを指します。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ちょろ根の状態の植物は、ちょっとしたストレスで発根が止まることがあるため、慎重に扱う必要があります。
追肥(ついひ、おいごえ):植物を植えた後に、成長を助けるために与える追加の肥料のことです。
すぐに効果が出る即効性の肥料を使うのが一般的です。
(⇔元肥)
接ぎおろし(つぎおろし):接ぎ木で大きく育った植物を、土台になっていた台木(だいぎ)から切り離し、土に植え直すことです。
接ぎおろしをすることで、もとの植物が台木に頼らず、自力で根を張って成長できるようになります。
接ぎ木(つぎき):成長の遅い植物を、丈夫で成長が早い別の植物につなぎ合わせて、育てる方法です。
土台となる植物の力を借りて、つないだ植物を強くし、成長速度を上げられます。
特に、同じ「属」に分類される植物同士は相性がよいため、接ぎ木の成功率が高まります。
この方法はおもにプロの生産者が行いますが、接ぎ木された状態で販売されている植物も、少なくありません。
爪(つめ):葉の先端にある、指の爪のように尖った部分を指します。
おもに「エケベリア」や「グラプトペタルム」、「グラプトベリア」などに使われる言葉です。
底面給水(ていめんきゅうすい):通常のように、上から水を与えるのではなく、鉢底から水を吸い上げさせる方法です。
鉢を水を入れた受け皿などに置いておくと、鉢の中の土が徐々に水を吸い上げます。
この方法だと、葉や花に水がかかるのを防げるため、特にシクラメンなどの植物に適しています。
多肉植物には種子はとても小さい品種もあるため、上から水をかけると流れてしまうことがありますが、底面給水であればその心配がありません。
底面給水は、以下の記事でご紹介しています。
綴化 (てっか):植物の成長点が突然変異を起こし、帯のように平らに変形する現象です。
この現象が起こると、植物は通常とは異なるユニークなすがたになるため、価値が高まり、高価になる傾向があります。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
石化と似た言葉ですが、綴化は植物の成長点が繋がった状態で、成長点が異常に増えた状態が石化です。
展着剤(てんちゃくざい):農薬などの薬剤が植物にしっかり付着するようにする、いわば「ノリ」のような役割の薬剤です。
他の薬剤と混ぜて使います。
溶ける(とける):溶けてしまったアイスのように、原型を留めず、植物が枯れてしまうことです。
植物が溶ける原因は、水やりのしすぎや、高温多湿により雑菌が繁殖して起こります。
いちど溶けた部分は、元に戻すことができません。
虎斑 (とらふ) :虎が身にまとう柄のように、葉に横向きに入る縞模様の斑(ふ)のことです。
胴切り (どうぎり):植物を水平方向に切り分けて、株数を増やす方法です。
- 切り分けた上の部分
- 成長点が残っているため、根っこを生やし、あたらしい個体として育つ
- 切り分けたあと、下に残った部分
- 成長点を失い、子孫を残すために、あたらしい子株を吹く
.jpg)
.jpg)
.jpg)
うまくいけば、10個以上もの子株を吹くこともあります。
土壌改良剤(どじょうかいりょうざい):土壌の通気性や保水性、水はけをよくする園芸資材です。
土を理想的な状態にすることで、植物の根張りがよくなり、健康的な成長を促します。
徒長(とちょう):植物の茎や葉が、ヒョロヒョロと間延びしてしまう現象です。
日照不足や風通しの悪さ、水のやりすぎなどが原因で起こります。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
100円ショップの売り場は日照が不足しがちなため、徒長したサボテンやエケベリアを見かけることが少なくありません。
トップスパイン:アガベなど植物の先端にあるトゲのことで、「トップスピン」とも呼ばれます。
トリコーム:ディッキアなどの葉の表面を覆う、白い毛状の構造体のことです。
トリコームを身にまとった植物は、特徴的な白っぽい見た目をつくり出します。
トリコームが剥がれると色が薄くなってしまうので、水は株に直接かけず、株元に水を与えたり、底面給水で水やりをしたりするのがおすすめです。


ナ行
中斑 (なかふ):葉の中心部分だけに、模様(斑)が入っている状態のことです。
ナーセリー:植物を生産し、販売する場所や業者のことを指します。
多肉植物では、特に海外の生産農家を意味することが多いです。
夏型 (なつがた) :夏の暑い季節に、勢いよく成長する植物の総称です。
しかし地球温暖化によって、夏は過酷な高温環境下になっているため、夏型の品種でも春や秋の方がよく成長することもあります。
難物(なんぶつ):枯らさずに育てるのが、非常にむずかしい植物のことです。
四季のある日本の気候や風土に、なじみにくい植物に対して使われる言葉です。
~錦 (にしき) :斑入りの品種に与えられる品種名の一部です。
この呼称を品種名の後ろに付けることで、その植物が白色や黄色の斑入り品種であることを示します。
抜き苗(ぬきなえ):植物を鉢から抜き、根に付いた土を落とした状態のことです。
軽量化によりコストが削減できるため、フリマアプリなどで、抜き苗の多肉植物が流通するケースはめずらしくありません。
沼・沼る(ぬま・ぬまる):多肉植物の魅力にどっぷりとハマり、夢中になって抜け出せなくなる状態を指します。
根挿し(ねざし):植物の根の一部を切り取り、それを土に植えることで、あたらしい個体を発生させる増やし方です。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
根挿しは、生命力が強い植物だけができる繁殖方法です。
根詰まり(ねづまり):鉢の中が根でギュウギュウになり、根を成長させるスペースがなくなっている状態を指します。
根詰まりを起こすと、以下の点から生育不良につながる可能性があります。
- 水はけが悪くなる
- 水や肥料を吸い上げられなくなる
- 根腐れのリスクが高まる
根鉢(ねばち):植物を鉢から抜いたとき、根と土が一体になった塊のことです。
根張り(ねばり):鉢の中で根っこがしっかり土を掴み、成長することを意味します。
日照 (にっしょう):直射日光が当たっている状態のことです。
根腐れ (ねぐされ):植物の根が、腐ってしまうことです。
土が乾かない状態が続くと、根が呼吸できなくなり、雑菌が繁殖して根腐れを起こします。
ここまで、ア~ナ行の多肉植物にまつわる専門用語を解説しました
.jpg)
.jpg)
.jpg)
かなりの長文になってしまうので、ハ~ワ行の専門用語については、以下の記事で解説しています。
よろしければお読みください
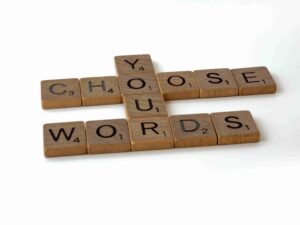
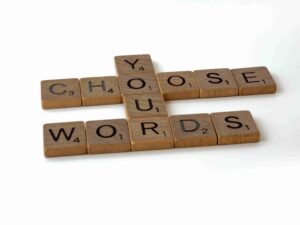
コメント