一から育てる塊根植物
個性的なルックスで人気を集める塊根植物の中でも、特に目を引くのが「プセウドボンバックス・エリプティクム(pseudobombax ellipticum)」です。
そのプックリとした塊根は、見るひとを惹きつける魅力に溢れています。
発芽直後の愛らしいすがたから、成長していく過程などを、写真とあわせて掲載しています。
同じ環境で育てても、株ごとの個体差が生まれるなど、実生ならではの奥深さも感じていただけるはずです
プセウドボンバックス・エリプティクムの基本データ
原産地:グアテマラ、インド
科・属:キワタ(パンヤ)科・プセウドボンバックス属
学 名:Pseudobombax ellipticum(プセウドボンバックス・エリプティクム)
プセウドボンバックス・エリプティクムは塊根植物
塊根植物とは根や茎を肥大させる植物
「塊根植物」は他の植物より、根や茎を肥大させ、ユニークな見た目をした植物のことを言います。
肥大させた部分に多くの水分を蓄えられるため、乾燥が進む地域でも枯れにくくなります。
ボンバックスは塊根植物として楽しまれている
「ボンバックス」は、ユニークな形状をした塊根植物として、観賞用に楽しまれています。
ですが、原産地では塊根植物と言うより一般的な樹木として暮らし、その大きさは樹高20mほどまで成長した株も見られます。
まん丸な塊根部分に仕立てるのはむずかしい!?
「ボンバックス」は、ガーデニングショップで販売されることもありますが、塊根部がまん丸な株はそう多くありません。
.jpg) 筆者
筆者塊根部を丸く仕立てるのは、カンタンではないのでしょう。
まん丸「ボンバックス」を入手するべく、たねを購入して、蒔くことにしました。
たねの購入先&発芽率
「ボンバックス」のたねは、ガーデニングショップなどでは販売されていないため、ネットショップで購入しました。
たねの購入ルートについては、以下の記事で詳しくご紹介しています
第1回目:2023年8月中旬
多肉植物ワールドでたねを購入しました
2023年8月中旬、「多肉植物ワールド」にたねが入荷した情報を入手したので、5粒入りの商品を2セット購入しました。
おまけとして、1粒ずつ入っていたため、実際に蒔いたたねの数は「5粒+おまけ1粒×2セット=計12粒」です。
ちなみに「多肉植物ワールド」は、植物をたねから育てる「実生(みしょう)」が好きなら、押さえておきたいネットショップ。
以下にリンクを貼っているため、ご興味があれば覗いてみてください
発芽率は16.7パーセントという結果に…。
たねを蒔いてから、水を切らさないように管理しましたが、最終的に2粒しか発芽しませんでした…。
- 2粒(発芽した数)/12粒(蒔いた数)=約16.7パーセント(発芽率)
ロットによっては、100パーセントに近い確率で発芽することもあるため、残念な結果です…。
発芽率は、たねの鮮度が影響する
「ボンバックス」をはじめ、多肉植物のたねは、鮮度がよければ発芽率が高い傾向にあります。
ただし裏を返せば、鮮度が悪いたねは発芽率が悪くなることに…。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
発芽率が低かったため、今回は、鮮度がよくなかったのかもしれません。
第2回目:2023年9月下旬
seed stock(シードストック)でたねを購入しました
第1回目の実生チャレンジから約1か月後に、「seed stock」で「ボンバックス」のたねの入荷情報を見つけました。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
また発芽率が低かったら、どうしよう…。
と購入を迷いましたが、「ボンバックス」のたねは、国内のネットショップで入手できる確率は低いため、あらためてチャレンジすることにしました。
今回も10粒購入したところ、おまけで2粒入っていたため、12粒を蒔きました。
今回の発芽率は66.7パーセントでした
- 8粒(発芽した数)/12粒(蒔いた数)=約66.7パーセント(発芽率)
多肉植物の実生の世界では、これだけの数が発芽したら、なかなか高い発芽率と言えます。
たねを蒔いた環境
「ボンバックス」のたねを蒔いた環境は、以下のとおりです。
- 日当たり=1~2時間ほど直射日光が当たる屋外
- 温度=最高気温が20℃以上
- 水やり=土が乾かないように、毎日水やり
- 水を溜めた容器に鉢を浸ける「腰水」は行わず
- その他の環境
- 風通しのよい屋外
- 多肉植物用の培養土を使用
多肉植物の「たねの蒔き方」については、以下の記事で詳しくご紹介しています
たねの蒔き方も発芽率に影響を与えるため、ご興味があればお読みください
プセウドボンバックス・エリプティクムの実生記録
2023年10月13日(October 13, 2023)
発芽したばかりの「ボンバックス」の様子です。
-1024x768.jpg)
-1024x768.jpg)
- 写真の左側に映る「ボンバックス」
- 最初に蒔いたたねから発芽した株(多肉植物ワールド産)
- 右側に映る「ボンバックス」
- 2回目のたね蒔きで発芽した株(seed stock産)
たね蒔きから1~2か月が経ち、最初に展開する‟子葉”の段階を経て、‟本葉”を広げている株も見られます。
葉の形状がハート形
キレイな子葉が展開しない
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ボンバックスの実生をして感じたのは、子葉がキレイな状態で展開しないという点です。
シワが入った子葉や、葉焼けのような茶色っぽい子葉が多いため、そのまま枯れないか心配になります。
中には、枯れてしまいそうな株も…。
多くの株は順調に育っていますが、芽を出しかけた状態のまま、成長が進まない株も見られます。
②-768x1024.jpg)
②-768x1024.jpg)
茶色の硬い殻を脱ぎ捨てるために、頑張っていますが、なかなか脱げないようです…。
「ボンバックス」は強い品種ですが、無事に芽を出せるでしょうか!?
2023年10月20日(October 20, 2023)
前回の記録から、1週間が経過しました。
-697x1024.jpg)
-697x1024.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
細い茎の上に大きな葉を何枚も広げているため、強風の際に茎から折れないか、心配になります…。
品種を問わず、硬いたねの殻を破るエネルギーには、植物の力強さを感じます
ただし、まだ殻を脱ぎ切れていない株もいるため、脱皮の作業を完了してほしいところです。
2023年11月4日(November 4, 2023)
前回の記録から、約2週間が経過しました。
①-768x1024.jpg)
①-768x1024.jpg)
-768x1024.jpg)
-768x1024.jpg)
茎が茶色く変色してきました
もともと緑色をしていた茎が、茶色く変色してきています。
この変色は、「木質化」(もくしつか)と言い、サボテンや多肉植物によく見られる現象です。
- 自重を支えたり、風で折れたりしないように株を丈夫にする
- 木質化した部分は硬くなる
- 乾燥に強くなる
- 木質化した部分からは、水分が逃げにくくなる
木質化した面積の分だけ、光合成できる量が少なくなる!?
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ボンバックスも木質化が進むと、幹の部分から葉緑体が減るため、光合成の効率が下がると考えています。
光合成より、強風で茎が折れる危険性を回避することが、「ボンバックス」にとっての優先事項のようです。
多くの「ボンバックス」が風の強い地域か、または乾燥が進む地域に、自生しているのかもしれません。
ちなみに、少し大きく育った「ボンバックス」を購入し、その後の成長記録を以下の記事でご紹介しています
2023年12月30日(December 30, 2023)
前回の記録から、約2か月が経過しました。
たねを蒔いてからだと、およそ3か月が経っています。
-768x1024.jpg)
-768x1024.jpg)
今は年末で、屋外は厳しい寒さが訪れているため、本来「ボンバックス」が葉を落として休眠する季節です。
自宅では15℃以上ある室内に置き、植物育成用のLEDライトを当てているため、現時点で休眠した株はありません。
ただし室内とは言っても、加温設備は使用していないため、もうすぐ休眠に入りそうです。
ちなみに、室内で使用している植物育成用のLEDライトは、以下のBRIM製のパネル型のものです。
強い光を必要とするアガベも、徒長せずに成長しているため、コスパよく植物を育成したい場合におすすめです
2024年1月22日(January 22, 2024)
前回の記録から、1か月半が経過しました。
-1024x768.jpg)
-1024x768.jpg)
濃い緑色の葉色をした「ボンバックス」もいますが、葉色が黄色く変色してきている株も見られます。
室温が12~13℃ほどに下がってからも、休眠させないために、土を乾かさないように育ててきましたが、間もなく休眠に入りそうです。
落葉しはじめたら、水を吸い上げなくなるため、徐々に水やりの回数を減らす予定です。
2024年5月24日(May 24, 2024)
たねを蒔いてから、約8か月が経過しました。
前回の記録からだと、約4か月が経っています。
結局、2月ごろにすべての株が落葉し、休眠状態に入っていました。
-768x1024.jpg)
-768x1024.jpg)
全体的に「ボンバックス」の木質化が進み、茎を色付ける茶色が濃くなりました。
塊根部に大きな成長は見られませんが、「ボンバックス」が春の成長期を迎えたため、冬が来るまでに、大きく成長することを期待しています。
株ごとに個体差があらわれはじめました
早くも、それぞれの塊根部に個体差があらわれています。
- 将来的に、まん丸な塊根植物に成長を遂げそうな株
- 塊根部の形成は、これからといった株
.jpg)
.jpg)
.jpg)
株ごとの個体差を感じ取れるのも、実生の楽しみ方のひとつです
まん丸な塊根部に仕立てるには、強剪定が必須
自宅の「ボンバックス」は、サイズ感が小さいため、強剪定をするには早すぎるでしょう。
もう少し大きく成長したら、強剪定を繰り返し行っていく予定です。
ちなみに以下の記事では、大きめな「ボンバックス」を、強剪定したときのことをご紹介しています
使用している鉢はスリット鉢
「ボンバックス」のたね蒔きから、その後の育成にいたるまで、スリット鉢(プレステラ90)を使用しています。
スリット鉢は、通気性や排水性に優れ、他にもメリットが多い鉢です。
以下の記事で、スリット鉢のメリットやデメリットについて、詳しくご紹介しています
特に、乾燥した環境を好む多肉植物との相性がよいため、ご興味があればお読みください
2024年10月6日(October 6, 2024)
たねを蒔いてから、1年以上が経ちました。
-1024x768.jpg)
-1024x768.jpg)
春に勢いよく芽吹いたものの、その後は、想像よりもゆっくりと成長しています。
あと1~2か月経つと休眠期に突入するため、秋の成長期で、2024年最後の成長を見せてほしいです。
どの株も同じ環境で育てていますが、一部の株は一向に塊根部が形成されず、ヒョロヒョロした見た目のままです…。
2025年6月22日(June 22, 2025)
前回の記録から、8か月半が経過しました。
それぞれの「実生ボンバックス」を、単独の鉢に植え替えました。
-768x1024.jpg)
-768x1024.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
今年は全体的に調子が上がらず、今にも枯れそうな小さな株もいますが、あたらしい鉢で大きな成長を見せてほしいです!
写真では9株しか映っていませんが、今のところ1株も枯れていないため、10株の「ボンバックス」が成長をつづけています
今後も、自宅で育てている「実生ボンバックス」の成長記録を付けていきます
(更新中)
自宅で育てている多肉植物の実生の記録は、以下の記事でまとめています
「ボンバックス」以外にも魅力的な品種をご紹介しているため、よろしければお読みください
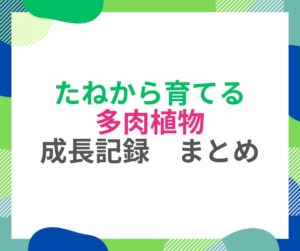
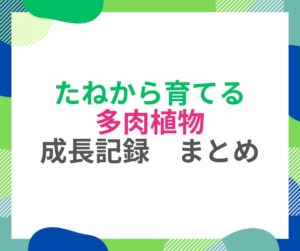
コメント