寒さから植物を守る
植物を育てる楽しさは、その成長を見守りながら、日々の変化や季節ごとに魅せる違った顔を、間近で感じられるところにあります
日本の四季は、“春一番”が吹く「春」や強い日差しが降りそそぐ「夏」、実りの季節である「秋」、そして厳しい寒さを伴う「冬」が到来します。
この寒さは、特に熱帯原産の植物や環境の変化に敏感な植物にとって、試練の季節となるでしょう…。
実際に、冬に植物を枯らした経験がある方は、少なくないと思います。
本記事では、植物が冬に枯れる原因を解説し、具体的な寒さ対策をご紹介します!
室内へ取り込むことや、簡易ビニール温室の利用など、どなたでも実践しやすい方法をまとめました
大切な植物を寒さから守り、暖かい春を一緒に迎えるためには、コツが必要です。
ぜひ、本記事の内容を参考のひとつにしてください
.jpg)
厳しい寒さで植物が枯れる「3つ」の理由
そもそも、なぜ植物は、寒い冬に枯れてしまうことがあるのでしょうか!?
植物が枯れる理由は多岐にわたりますが、この季節に植物が調子を崩しやすくなる原因を、3つご紹介します。
自生地と日本の気温差
もともと日本の自然の中で暮らしている植物は、昔から四季のある環境に馴染んでいるため、寒さが到来する季節にも耐性をもっています。
自らが寒さに耐えられるように進化した品種だけではなく、「タネ」という子孫をつくり、そのすがたで冬を乗り切る品種もいます。
日本では、世界中で自生する植物が育てられ、楽しまれています
世界中の植物は、それぞれの自生地の環境に馴染んでおり、品種ごとに耐えられる寒さは異なります。
たとえば、多くの観葉植物が『耐寒温度:10℃程度』と言われるのは、自生地では10℃以下になる日が、ほとんど訪れることがないため。
凍結
「凍結」も、植物が枯れてしまう原因のひとつ。
寒さに強い植物は、気温の低下とともに体内の糖分を増やし、樹液を凍りづらくしています。
しかしそれでも、植物の中に蓄えられている水分が、凍ってしまうこともあります。
体内に溜めている水分が凍結すると、氷の結晶により細胞が傷つけられることに…。
暖かい春を迎えると降り積もった雪は溶けますが、いちど傷ついた細胞は、暖かくなっても元の形状には戻れず、最悪の場合には枯れてしまいます。
根腐れ
土が濡れたままの状態が続くことで、植物の根が呼吸できず、「根腐れ」を起こすことも、寒い季節に起きやすいトラブルです。
以下の理由から、冬は濡れた土がなかなか乾きづらい季節。
- 太陽が昇ってる時間が短い
- 気温が低い
- 気温が低いと、空気中の水蒸気量が小さくなる
また、ひとが汗をかくのと同じように、植物は葉から水分を蒸発させることで、体温調整を行っている生き物。
(これを「蒸散」と言います。)
暑い季節は、体温調整のために多くの水分を蒸散させますが、冬は体温を調整する必要がない分、蒸散させる量は減っていきます。
また、植物の成長期ではないことからも、そこまで多くの水分を必要としない季節。
たとえ根腐れを起こさなくても、土がいつまでも濡れた状態では、鉢内で雑菌が繁殖し、植物によい影響を与えることはありません。
なお、冬以外の季節でも、植物が枯れてしまうことはあります。
植物が枯れる理由は、下記の記事で詳しくご紹介しているので、ご興味があればお読みください
植物を枯らさないための「13個」の寒さ対策
寒さ対策は、カンタンな方法もあれば、少し取り組みにくい方法もあります。
室内に取り込む
もっとも確実な寒さ対策は、植物を「室内に取り込む」ことです。
エアコンが効き、15℃以上の室温がキープされている状態がベストです。
しかし、室内ではエアコンを使用していなくても、冷蔵庫やTVなどの熱などによって、屋外より暖かい環境が自然とつくられます。
室内に取り込むことは、デメリットや注意点がいくつかあるので、ご紹介しておきます
日照不足で、徒長のリスクが上がる
室内では太陽の光を確保しづらいので、日照不足により、枝葉などが間延びする「徒長」を起こすリスクが高まります。
植物を室内に取り込む場合は、なるべく意識して日の光に当てることで、徒長を防止することができるでしょう。
室内で光量が確保できない場合には、植物育成用LEDライトの活用も、検討が必要です。
特に、強い光を当てる必要がある多肉植物を室内で育てるためには、園芸グッズを揃えた方が安心です
多肉植物の室内育成は、下記の記事で詳しくご紹介しています
育成場所の分だけ、生活スペースが削られる
また育成スペースの分だけ、室内での生活スペースが削られることになります。
多くの植物を室内に取り込むと、冬のあいだは、部屋が“ジャングル化”してしまうことにも…。
.jpg)
室内に取り込む前に、害虫のチェックをする
室内に取り込む前には、植物に害虫が付いていないか、チェックすることが必要です!
暖かい環境は害虫にとっても棲みやすい環境であるため、誤って植物と一緒に害虫を取り込んでしまうと、室内で害虫が増殖する可能性があります。
害虫(コバエ)対策については、下記の記事で詳しくご紹介しています。
急激な環境の変化にも、注意が必要
また、屋外の植物を室内に取り込む場合は、『急激な環境の変化』が生じます。
屋外と室内の温度差が、20℃近く発生することもあるでしょう。
たとえ環境がよくなる場合でも、『急激な環境の変化』は、植物にとって大きなストレスを与えます。
寒い屋外から暖かい室内にいきなり移動すると、温度差が激しく、急激な環境の変化が起こります。
まずは暖かい室内よりも涼しい玄関などのスペースで、1~2週間ほど慣らせてから室内に取り込むことで、環境の変化を緩やかにすることができます。
寒さを凌ぐために行った対策によって、植物が体調を崩してしまっては、元も子もありません。
(簡易)ビニール温室を利用する
「簡易ビニール温室」は、コンパクトなものが多いですが、結構な株数を格納しておけるタイプもあります!
ただし、ビニール自体の強度は高くなく、自宅ではワンシーズンでビニールの一部に穴が開き、使えなくなってしまいます。
これから導入する場合は、ビニールを追加で購入する費用が発生することは、考慮しておく必要があるでしょう。

「簡易ビニール温室」は、ガーデニングショップだけではなく、ホームセンターなどでも販売されているので、入手しやすい点もメリットです。
ただし「簡易ビニール温室」については、一長一短あるのも事実。
下記の記事で詳しくご紹介しているので、導入を検討されている方は、参考にしてみてください
マルチング材を使用する
バークチップやウッドチップなどの資材で、植物の株元を覆うことは、「マルチング」と呼ばれる園芸手法です。
マルチングのメリット
「マルチング」には保温効果もあるので、植物の根を寒さから守る役割を果たし、それ以外にも以下のようなメリットがあります!
- 害虫が、土の中に侵入することを防ぐ
- 雑草対策(雑草のタネが飛来してきても、土に根付かせない)
- 土からの水分蒸発を防ぎ、乾燥を防止する
マルチングのデメリット
「マルチング」を導入することで、以下のようなデメリットが発生します。
- 土の乾き具合が、分かりづらくなる
- 水やりの難易度が上がる
- 土の上から使用するタイプの固形肥料を、使用しづらくなる
- 鉢の中の通気性が悪化する
- マルチング材を購入するための費用が、別途で発生する
無料で入手できるマルチング材
市販のマルチング材を購入せずに、無料(タダ)で入手し、代用することもできます。
その代用品は、「雑草」です
逆に“広葉雑草”と呼ばれる、タンポポやクローバーなどは、マルチング材には向いていません。
雑草をマルチング材に代用するときは、その雑草のことをよく調べてから、活用しましょう!
軒下に移動する
屋外の屋根の下の部分にあたる「軒下(のきした)」があれば、この軒下を利用することも、寒さ対策になります!
軒下は、雨に当たりづらくなり、植物の大敵である「霜」も降りにくい環境です。
水分量を下げれば、寒さに強くなる
植物は、体内に蓄えている水分量が減少すると、寒さに強くなる性質をもっています。
軒下にいる植物は、強風を伴う雨が降らない限り、雨に当たらないので、水やりをしなければ、体内の水分量が徐々に減っていきます。
軒下であれば、室内の生活スペースも取らず、寒さ対策のグッズを買い揃える必要もありません!
もしも、軒下のスペースが空いているなら、積極的に活用しましょう!
フラワースタンドorガーデンラックを使用する
鉢を、コンクリートなどの地面に直接置いている場合、地表の冷気が鉢を通して、植物の根に伝わります。
地表からの冷気を防ぐために、フラワースタンドを使用して鉢を地面から離したり、ガーデンラックに鉢植えを置いたりすることで、寒さ対策が講じられます。
フラワースタンドorガーデンラックのメリット
フラワースタンドは、寒さ対策以外にも、メリットが多いグッズです。
- 鉢底やスリットなどからの害虫の侵入を、防止することができる
- 多段式のラックは、上下のスペースも有効活用できる
- 風通しや日当たりを、向上させることができる
- コンクリートの照り返しによる熱を、防ぐことができる(暑さ対策)
フラワースタンドorガーデンラックのデメリット
デメリットは、ほとんどありませんが、あえて挙げるなら、フラワースタンドが転倒すると、植物に大きなダメージを与えることです。
多段式のラックの場合、下段に重量のあるものを設置することで、転倒防止策を取ることができます。
ステンレス製orアルミ製は錆びづらい
フラワースタンドは、100円ショップでも入手できます。
ただし、100円ショップのものは、1鉢だけに使用できるものが基本。
育てている鉢数が多い場合は、多少高価でも、多段式のガーデンラックを購入することがオススメです!
リーズナブルに入手できるものは、スチール製のものが多いです。
しかし、スチール製のものは錆びやすいので、長いあいだ使用するのであれば、違う材質のものを選びたいところ。
鉢を二重にする
『鉢を二重にする』ことも、植物に取れる寒さ対策のひとつ。
特に保温効果の高い鉢は、プラスチック鉢です。
プラスチック鉢を二重にかぶせるだけで、直接風が鉢に当たりづらくなるため、保温効果をUPさせることができます。
また、鉢に「気泡緩衝材」を貼り付けることも、二重鉢と同じ効果が生まれますが、見た目は二重鉢の方が優れているのかもしれません。
「気泡緩衝材」は、通称“プチプチ”と呼ばれ、食器類の梱包などに使われるものです。
日によく当てる
日によく当てることで、植物の耐寒性を向上させることができます!
熱量を体内に保てることができ、生き抜くためのエネルギーをつくり出せるので、寒さだけではなく、さまざまな面で日光浴は大切な要素です。
寒さに徐々に慣れさせる
自然の中では、季節による気温差がありますが、気温は徐々に変化していくものです。
『今日まで最高気温が35℃を超えていたのに、明日以降は10℃までしか上がらない。』ということはありません。
植物は徐々に変化していく環境に馴染んでいるので、寒さに当てる場合でも、徐々に慣れさせる過程が重要です。
昼と夜で気温が30~40℃も違うという、寒暖差の大きい“砂漠”というエリアも存在します。
ただし、砂漠には植物がほとんど育っていません。
多くの植物が育つエリアには、昼と夜の寒暖差が大きくないことが一般的です。
数年単位で、徐々に寒い環境に慣れさせることによって、植物が想像以上に寒さに強くなることもあります。
実際に、自宅では耐寒温度10℃の観葉植物を、徐々に寒い屋外に慣らして、今や1~2℃まで下がる場所でも無傷で育てられるようになりました!
品種ごとの耐寒性を知る
どれだけの寒さに耐えられるかは、品種ごとでさまざま。
特に寒さへの対策を取らずに、雪や霜の影響を受けても、問題なく越冬できる植物もいます。
水は室温で温めてから植物に与える
東京都水道局によると、東京都内でも真冬の季節は、水道水の水温が7〜8℃まで下がっているそうです。
水道水の温度のまま水やりをしてしまうと、水温の低さから、植物がストレスを感じるでしょう。
植物に水やりをするときは、水を溜めたじょうろを、半日~1日以上は室温で温めてから水やりをすることで、植物へのストレスを軽減させることができます!
ただし、植物が水切れを起こしている状態など、すぐに水やりをすることが望ましい状況もあるでしょう。
「水やりをした後には、じょうろに水を溜めておく」ことをルーティン化すると、植物への水やりのタイミングを逃す心配がありません。
-2.jpg)
水やりの頻度、1回あたりの量を減らす
植物の体中に蓄えている水分を減らす目的で、水やりの回数を減らすことも、寒さ対策に有効な方法です。
ただし、土が乾きづらい季節なので、土の乾き具合は日々の観察が望まれます。
いつまでも土が乾かないぐらいなら、水やりを減らした方が、植物にとってよい影響を与えます。
1回の水やりで与える水の量も、1週間ほどで完全に乾く量に調整することで、水やりによる失敗を減らせるでしょう。
少量の水やりだと、根に水が行き届かない可能性があるので、葉水をこまめに与えるなどの水切れ対策は必要です。
便利なガーデニンググッズの存在(水差し)
少量の水を与えるのであれば、少しずつ水が出てくる便利な「水差し」が、100円ショップでも売られています!
.jpg)
この「水差し」のよい点は、株元にピンポイントで水を与えられるので、水を与えにくい場所にある鉢もカンタンに水やりができます。
反対にデメリットは容量が小さいので、育てている植物の数が多い場合は、この商品だけで水やりするのが、むずかしい点。
税込110円なので、お試し感覚で利用してもよいかもしれません。
Amazonなどでも、類似品の入手が可能です
水やりの基本は、下記の記事で詳しくご紹介しています
よろしければ、あわせてお読みください。
風が直接当たらないようにする
『風速1mの風に直接当たると、体感温度が1℃下がる』と言われていますが、これは植物にとっても、同じことが当てはまります。
吹く風が強ければ強いほど、植物は厳しい寒さを感じるので、風を防ぐことが寒さ対策になります。
段ボールや発泡スチロール、ビニール、不織布などを使用し、風が直接当たらない環境をつくることも、冬越しへの手助けとなるでしょう。
植物ごと包むことがむずかしい場合は、鉢の部分を段ボールや発泡スチロールなどで覆うだけでも、寒さから根を守ることができます。
.jpg)
冬前に、植え替えや剪定をしない
植え替えや剪定は、植物にとって大きなストレスを与えます。
秋に植え替えなどの園芸作業を行う場合は、冬にはストレスから完全に回復できているように、秋に差しかかったタイミングで行うことが望まれます。
春まで園芸作業をすることを待てるのであれば、春まで待った方が無難です!
なるべく、冬はストレスフリーな状態で迎えることが重要です。
まとめ
寒い冬は植物にとって厳しい季節ですが、望ましい対策を講じることで、大切な植物と春を迎えることができます!
本記事では、植物が冬に枯れてしまう原因を解説し、さまざまな寒さ対策を紹介しました!
それぞれの方法にはメリットと注意点があるため、植物の品種やそれぞれの育成環境に応じて、最適な方法を選びましょう!
また、植物を寒さに慣らす過程や、急激な環境変化への配慮も重要です。
寒さ対策を知っていることで、すでに育てている植物を枯らさずに育てることができ、あたらしく植物をお迎えするハードルも低くなります。
今は実店舗だけではなく、ネットショップでも植物を入手できます。
ネットショップなら、園芸店の営業時間を気にする必要がなく、ひとりでは持ち運べない植物も購入しやすいものです
以下の記事で、観葉植物を扱うオススメのネットショップをご紹介しているので、よろしければ参考にしてみてください
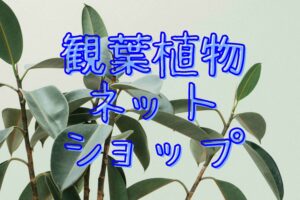
コメント