ウリ科の塊根植物
植物とは思えないそのすがたに、思わず目を奪われるのが「塊根植物」です。
本記事では、「ゲラルダンサス・マクロリザス」を種から育てている記録をご紹介します
発芽したばかりの幼苗が冬を乗り越え、目覚ましく成長していく様子からは、植物の力強さを間近に感じられます。
園芸初心者の方も、すでに愛好家の方も、ウリ科の塊根植物の魅力にどっぷり浸れること間違いなしです!
ゲラルダンサス・マクロリザスの基本データ
原産地:南アフリカ・東ケープ州
科・属:ウリ科・ゲラルダンサス属
学 名:Gerrardanthus macrorhizus(ゲラルダンサス・マクロリザス)
別 名:眠り布袋(ねむりほてい)
ゲラルダンサス・マクロリザスの特徴&たね蒔きどき
ゲラルダンサス・マクロリザスの特徴
「ゲラルダンサス・マクロリザス」は、春から秋までの暑い(暖かい)季節が成長期の“夏型”の塊根植物です。
寒さを苦手としているため、冬のあいだは葉を落とし、休眠状態になります。
ゲラルダンサス・マクロリザスのたねの蒔きどきは春か秋
春がベストだが、秋にも蒔ける
「ゲラルダンサス・マクロリザス」の発芽温度は20~25℃のため、暖かい季節にたねを蒔くのがベストです。
発芽後の成長のことを考えると、春がベストなタイミングですが、秋に蒔くこともできます。
たねを秋に蒔いた株を冬越しさせるためには、対策が必要
春にたね蒔きをした株は、冬までに半年ほどのスパンがあるため、1年目の株でも冬越しできる体力をつけやすいです。
ただし秋にたねを蒔くと、休眠期までの期間が短い分、株が大きく成長できず、十分な体力が養われないまま冬を迎えることになります…。
秋にたねから発芽した1年目の株は、冬に休眠しないように、強い光と暖かい温度を確保するのが理想です。
ただし植物育成用のLEDライトを使用したり、暖かい温度を保ったりするためには、それなりに電気代が発生します…。
多肉植物の室内育成については、以下の記事で詳しくご紹介しているため、ご興味があれば参考にしてみてください
ゲラルダンサス・マクロリザスのたね蒔き後の経過
たね蒔き初日:2023年10月1日
たねは容易に入手できない
「ゲラルダンサス・マクロリザス」は、カンタンにたねを入手できるわけではありません。
季節は秋を迎えているため、このタイミングでたねを蒔くと、1年目の冬のあいだは、電気代をかけて室内で育成する必要がありますが、
.jpg) 筆者
筆者このチャンスを逃したら、次にいつ実生できるか分からないし…。
と考え、実生することにしました
たねは消毒せずに播種しました
「ゲラルダンサス・マクロリザス」のたねはカビるリスクは高くないようなので、今回はたねを消毒せず、風通しのよい屋外で、多肉植物用の培養土に蒔きました。
用土が濡れた状態を保てるように、水を入れた容器に鉢ごと浸ける「腰水」の状態で「ゲラルダンサス・マクロリザス」の発芽を待ってみます。
多肉植物のたねの蒔き方については、以下の記事で解説しているため、ご興味があれば参考にしてみてください
たね蒔き14日後:2023年10月14日
「ゲラルダンサス・マクロリザス」のたねを蒔いてから、14日が経過しました。
-768x1024.jpg)
-768x1024.jpg)
茎がしっかり直立し、最初に展開する子葉(しよう)を左右に広げている株もいれば、これから起き上がろうとしている株も見られます
①-768x1024.jpg)
①-768x1024.jpg)
多肉植物の実生は、せっかく蒔いたたねが発芽しなかったり、たねの殻を脱げないまま枯れたりと、すべてのたねが順調に発芽するケースは稀です。
ちなみに今回は「プレステラ90」という、黒いプラスチック鉢を使用しました。
鉢底の側面に切れ目(スリット)が入っていて、排水性や通気性に優れているため、乾燥した環境を好む塊根植物と相性がよい鉢です。
スリット鉢のメリットやデメリットについては、以下の記事で詳しくご紹介しています
たね蒔き20日後:2023年10月20日
「ゲラルダンサス・マクロリザス」のたねを蒔いてから、20日が経過しました。
-760x1024.jpg)
-760x1024.jpg)
どの植物でもそうですが、子葉と本葉では形状が異なります。
- 子葉(しよう)
- 左右対称に、縦長な形状をしている
- 葉の血管とも言える葉脈(ようみゃく)は、縦に入っている
- 本葉(ほんば)
- 葉はトランプのスペードのような形状をしている
- 葉は左右対称ではない(1枚ずつ展開)
- 葉脈の入り方も、子葉と異なる
たね蒔き35日後:2023年11月4日
たねを蒔いてから、35日が経過した「ゲラルダンサス・マクロリザス」です。
-2-768x1024.jpg)
-2-768x1024.jpg)
今はまだ塊根植物とは思えないすがたですが、さらに塊根部分が形成されると、塊根植物としての存在感が増すのではないでしょうか。
今は11月に突入していますが、最低気温は15℃以上あるため、直射日光が1~2時間ほど当たる屋外で育てています。
たね蒔き70日後:2023年12月9日
「ゲラルダンサス・マクロリザス」のたねを蒔いてから、70日が経過しました。
-768x1024.jpg)
-768x1024.jpg)
塊根植物の中では成長速度が早い
発芽してから2か月余りで、塊根部分が直径2cmほどまで大きく成長しました
耐寒温度は5℃程度
自宅の育成環境は、11月中旬から最低気温がひと桁に差しかかったため、今は室内で育てています
植物の寒さ対策については、以下の記事で詳しくご紹介しています
使用しているLEDライトはBRIM製
ちなみに、自宅で使用している植物育成用のLEDライトは、以下のBRIM製のパネル型のものです。
もっと強い光量を出せるライトも市販されていますが、このLEDライトはリーズナブルな割に性能が悪くないため、コスパに優れています。
たね蒔き91日後:2023年12月30日
「ゲラルダンサス・マクロリザス」のたねを蒔いてから、約3か月が経過しました。
-768x1024.jpg)
-768x1024.jpg)
「ゲラルダンサス・マクロリザス」はつる性の植物のため、周囲のものに絡まりながら枝葉を伸ばします。
室内の置き場所は、一段の高さが40~50cmほどある、多段式のガーデンラックの中段です。
室内に取り込んだときは周囲との距離感に余裕がありましたが、今は上段のラックにつるを絡ませそうなくらい、枝葉の成長が旺盛です。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ある程度のサイズまで成長したため、株に体力が備わり、今から休眠に入っても、春には問題なく目覚めるだろう
と考えていますが、今回の冬はなるべく休眠させずに、春まで育てていきます。
ちなみに「ゲラルダンサス・マクロリザス」は、少し大きく育った株をガーデニングショップで購入し、その後の成長記録を付けています
以下の記事でご紹介しているので、よろしければお読みください
たね蒔き231日後:2024年5月18日
前回の記録から、約半年が経過したときの様子です。
-1024x768.jpg)
-1024x768.jpg)
まだ1年経っていませんが、ひと目で「ゲラルダンサス・マクロリザス」と分かるすがたまで、成長を遂げています
ただし、休眠する前の調子がよかったころとは異なり、葉を黄緑色に染めた株も見られます。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
この株は展開している葉のサイズも小さいため、調子が悪そうです…。
最低気温が12~13℃に下がったタイミングで休眠に入った
冬のあいだ、エアコンを稼働させていない室内で育てていたところ、すべての株が2月ごろに落葉し、休眠に入りました。
「ゲラルダンサス・マクロリザス」が休眠を迎えたのは、室温が12~13℃ほどまで下がったタイミングです。
「ゲラルダンサス・マクロリザス」を休眠させたくない場合は、15℃以上の環境で水やりを継続していれば、葉を落とさずに冬を乗り越えられると思います。
たね蒔き372日後:2024年10月6日
「ゲラルダンサス・マクロリザス」のたねを蒔いてから、約1年が経過しました。
-1024x768.jpg)
-1024x768.jpg)
一方で、小さめな「ゲラルダンサス・マクロリザス」は、直径2~3cmといったところです。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
鉢に単独で植えられているか、他の株と同じ鉢に植えられているかによって、大きさに差が出ています。
それぞれの鉢に同じ数のたねを蒔きましたが、発芽しなかったたねもあるため、鉢内の株数に違いが出ています。
根を張れる土の量によって、株ごとの成長速度に差が出ているのでしょう。
環境が整った室内で育成するならまだしも、春から秋までの成長期を屋外で育て、これだけ大きく成長する塊根植物は、そう多くありません。
たね蒔き631日後:2025年6月22日
前回の記録から、8か月半が経過しました。
株同士がギュウギュウに押し合い、窮屈に見えたため、このタイミングで植え替えることにしました。
-1024x768.jpg)
-1024x768.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
根の量は、ものすごく多いわけではありませんが、調子はよさそうです!
写真の一番左側に映る株の塊根部分に、深さ1cmほどの穴が開いていますが、これは害虫に食べられた跡かもしれません…。
今は元気がよさそうなため、殺虫&防虫のスプレーを吹きかけて、このまま様子を見ていきます。
このタイミングは、最高気温が30℃を超えています。
植え替えの適期とは言えませんが、「ゲラルダンサス・マクロリザス」は強いため、暑い時期に植え替えても、大きな問題はないと思います。
①-768x1024.jpg)
①-768x1024.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
冬に水やりをしなさすぎたのが、枯らした原因だと思います。
ちなみに今回使用した培養土は、自宅で配合しているものです
以下の記事で配合割合をご紹介しているため、ご興味があればチェックしてみてください
アガベに焦点を当てて書いた記事ですが、自宅の多肉植物には全般的に使用している培養土です。
それぞれ単独の鉢に植え、根が張れるスペースが増え、あわせて固形肥料も補充したため、今後のさらなる成長に期待しています
(更新中)
自宅で育てている多肉植物の実生記録は、以下の記事でまとめています
「ゲラルダンサス・マクロリザス」以外にも魅力的な品種を育てているため、よろしければお読みください
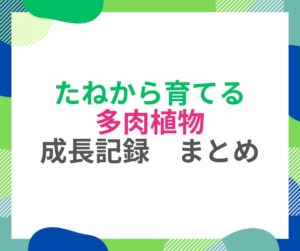
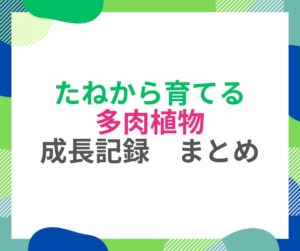
コメント