冬型のメセン
「コノフィツム」は成熟した株でも、直径が大きくならず、秋から春までの涼しい季節に旺盛な成長を見せる『冬型』の多肉植物です。
本記事ではそんな「コノフィツム」を、たねから育てる記録についてご紹介します
冬型メセン「コノフィツム」の基本データ
育 て 易 さ:★★☆☆☆(たねから育成するのは、若干むずかしい)
成 長 速 度:★☆☆☆☆
入手し易さ:★★★☆☆
耐 寒 性:★★★★☆(耐寒温度(目安):5℃)
耐 暑 性:★★★☆☆
原産地:南アフリカ・ナミビア
花言葉:似たもの同士
科・属:ハマミズナ科・コノフィツム属
学 名:Conophytum(コノフィツム)
冬型メセン「コノフィツム」のたねの購入
今回は多肉植物のたねを扱うネットショップ、「多肉植物ワールド」をチェックしていたところ、『コノフィツム・ミックス』という名前のたねを見つけました!
コノフィツム属の植物は、数百種類の品種が存在すると言われています。
「コノフィツム」の品種ごとの細かい特徴は分からないので、
いろいろな品種の「コノフィツム」を育ててみたい!
と思い、さっそく『コノフィツム・ミックス』のたねを購入し、蒔いてみることにしました
-768x1024.jpg)
購入した数は、50粒です。
多肉植物のたねは、ネットショップ「seed stock」から購入することが多いです。
「seed stock」の在庫に、欲しい植物のたねが見当たらなければ、たまに「多肉植物ワールド」をチェックしています。
これまでに、複数のルートでたねを購入し、植物を育ててきました。
以下の記事では、たねの購入先のレビューをご紹介しているので、ご興味があれば参考にしてみてください
冬型メセン「コノフィツム」のたねを蒔いた環境
多肉植物は『この方法でたねを蒔かないと、発芽しない』という方法が、存在するわけではありません。
ひとそれぞれで、たねの蒔き方は異なります。
一般的なたねの蒔き方については、以下の記事を参考にしてください。
たね蒔き用土
たね蒔き用土には、自宅の多肉植物を育成している『多肉植物用の培養土』を使用しました。
発芽したあとも、同じ培養土で育てていく予定です。
ちなみに、「赤玉土(あかだまつち)」、「鹿沼土(かぬまつち)」などの無機質の用土を混ぜており、配合割合は以下に記載の通りです。
- 赤玉土(小粒):3
- 鹿沼土(小粒):3
- 日向土(小粒):3
- くん炭:0.5
- パーライト:0.5
培養土の詳細は、以下の記事で詳しくご紹介しています
水やり
「コノフィツム」は、乾燥が進む環境でも暮らしていけるように、多くの水分を体内に蓄えているため、多くの水やりは不要です。
ただし株がまだ小さいうちは、体内に蓄えておける水分量が少ないため、多めに水やりをする必要があります。
たねを蒔いてから1~2か月ほどは、水を溜めた容器に鉢ごと浸ける「腰水(こしみず)」で管理しました。
このタイミングは、根腐れの危険性は低く、水不足のリスクの方が高いです…。
日当たり
夏の強い直射日光に当てると、成熟した株でも焼けてしまうことがあるため、なおさら避けた方がよいでしょう
自宅では室内の窓際でレースのカーテン越しの光を当てていましたが、それだけだと日照不足になると判断し、毎日2~3時間ほど、植物育成用のLEDライトを照らし光量を補いました
幼苗にとってメーカー推奨の照射距離で照らすと、光が強すぎるため、少し遠く(50cmくらい)の距離です。
風通し
風通しのよい屋外で育てる場合は特に問題ありませんが、室内で育てる場合は、サーキュレーターの使用が望まれます。
今回はたねが発芽するまではサーキュレーターを使用せず、発芽が確認できたあとは、サーキュレーターを稼働させている部屋に移動しました。
温度
「コノフィツム」が発芽するために必要な温度は15~20℃程度なので、なるべく適温を保つようにしていました。
夜間に10℃ほどまで下がったこともありましたが、発芽率に大きな影響はなかったと思います。
「コノフィツム」は涼しい環境が好きなため、秋に差しかかり、気温が下がってきたタイミングがたね蒔きの適期です。
地域やその年によっても異なりますが、9月~11月ごろがたね蒔きに望ましい季節です。
肥料
「コノフィツム」が発芽するためには栄養分を必要としないため、たね蒔き用土に肥料分は配合していません。
株が小さいうちから肥料を与えると、「コノフィツム」に
すでに栄養分が吸えているから、根をそこまで成長させなくてもいいか。
と思わせてしまい、その後の株の成長にとって、マイナスに働くことがあります。
冬型メセン「コノフィツム」のたね蒔き後の経過
たね蒔き時(2023年11月4日)
なるべく等間隔にたねを蒔く
たね同士が密集した状態で発芽すると、大きく成長するにつれて、株同士が成長を阻害する場合があります。
直前に水に浸けると、等間隔に蒔けなくなる
ただし「コノフィツム」のたねは、1mmに満たないサイズなので、いちど水に浸けてしまうと、たねを蒔くのがむずかしくなってしまいます。
今回はたね蒔き後、植物活力剤「メネデール」を薄めた水で腰水し、発芽を促しました。
多肉植物のたね蒔きは、多湿な環境で管理するため、カビが発生することも少なくありません。
ただし「コノフィツム」のたねからは、カビが発生することはありませんでした。
たね蒔きから4日後(2023年11月8日)
「コノフィツム」のたねを蒔いてから、4日が経過しました。
-768x1024.jpg)
よく確認しないと分からないくらい、ミニチュアサイズです
たね蒔きから8日後(2023年11月12日)
たねを蒔いてから、8日が経過しました。
-768x1024.jpg)
発芽率は、100%に近いのではないでしょうか!
ただし発芽率が高まるにつれて、たねを等間隔に蒔けていなかった状況が、浮き彫りになってきました…。
たね蒔きから15日後(2023年11月19日)
たねを蒔いてから、15日が経過しました。
-768x1024.jpg)
直近の1週間で、直径が1mmほど大きくなったのではないでしょうか
もともとがとても小さな植物なので、たった1mmでも、大きな進歩と捉えてよいでしょう
直径は大きく成長しているものの、株の形状は細長く、徒長しているように見えます…。
細長く成長した原因は光量不足かもしれないので、植物育成用のLEDライトが、現状より強く当たる場所に移動し、様子を見ます。
たね蒔きから35日後(2023年12月9日)
たねを蒔いてから、35日が経過しました。
前回の記録からだと、約3週間が経過しています。
-768x1024.jpg)
鉢内では、株同士が押し合う様子も…
「コノフィツム」が大きく成長するにつれて、鉢内では株同士が押し合う様子が確認でき、すでに場所取り合戦がはじまっているようです。
この高い人口密度を長く放置すると、いずれ戦いに負けた片方の「コノフィツム」が、枯れてしまうかもしれません…。
ただし株に体力がない状態で、下手に調整しようとすると、逆効果になることが多いので、現状のまま様子を見ます。
今のところ、成長速度はとても遅い
たね蒔きから1か月ほどしか経過していませんが、今のところ、成長速度はとても遅いです。
はじめて育てる場合、お花を咲かせるまでには、もっと長い期間を要するのかもしれません。
たね蒔きから56日後(2023年12月30日)
「コノフィツム」のたね蒔きから、56日が経過しました。
-768x1024.jpg)
今のすがたからは、「コノフィツム」とよく似た「リトープス」に見えるような気がします…。
コケが発生しました…
土の表面に、コケが生えてきました。
腰水で常に土が湿った状態だったので、コケにとっても、暮らしやすい環境だったのでしょう…。
これ以上、コケが発生しないように、このタイミングから腰水での管理はやめました。
たね蒔きから77日後(2024年1月20日)
「コノフィツム」のたね蒔きから、77日が経過しました。
年を越し、2024年を迎えています。
-768x1024.jpg)
体内に、たくさんの水分を蓄えている様子が伝わってきます!
光量を調整してからは徒長が進行せず、株の形状が、ズッシリとしてきました
さまざまな品種が混ざった「コノフィツム“ミックス”」ですが、現状のすがたからは、どの株も同じ品種に見えます。
腰水をやめてからも、多めに水を与えているので、コケの発生がどんどん進んでいます…。
室内育成では、コケの存在が厄介です。
多肉植物の室内育成については、以下の記事で詳しくご紹介しているので、ご興味があればお読みください
たね蒔きから184日後(2024年5月6日)
たね蒔きから、半年(184日)が経過しました。
-1024x768.jpg)
半分以上の株を枯らしてしまいました…
1~2か月ほど前まで順調に成長をつづけていましたが、ここに来て、半分以上の株を枯らしてしまいました…。
枯れた原因は、急激な温度変化だと思われます。
気温が上昇してきたタイミングでも、室内育成をつづけていたところ、急激に室温が高くなった日がありました。
茶色く枯れたような見た目は、休眠期に入るサイン
生き残っている「コノフィツム」も、黄色や赤などに身体を染めていますが、これは休眠期を迎えたサインです。
枯れているわけではないので、秋になれば、元気なすがたを取り戻すでしょう
コノフィツムは石などに擬態した植物
「コノフィツム」は周囲の石などに擬態するように進化した植物ですが、たしかにこうして見ると、どこにいるのか、非常に分かりづらいです。
厳しい寒さや暑い環境は避けるべき
「コノフィツム」は比較的寒さに強い植物ですが、それでも耐寒温度は5℃程度とされています。
特に株がまだ小さい状態では、冬のあいだに最低気温が0~1℃ほどまで下がる環境で越冬するのは、厳しいと思います。
また、原産地はそこまで高温にならないため、暑さに強くありません。
冬に室内に取り込んでいた場合、厳しい冬の寒さを乗り越えたら、春先には屋外に出した方がよかったのかもしれません。
たね蒔きから313日後(2024年9月12日)
たね蒔きから、300日以上が経過しました。
①-768x1024.jpg)
そして、使用している培養土(ひゅうが土や赤玉土の小粒)よりも大きく成長し、その存在感を発揮してきました!
冬型のため、気温が上昇したら、ほとんど成長しないだろうな。
と思っていましたが、5~9月の春から夏の季節が、もっとも大きな成長を見せているのではないでしょうか。
暑い季節がつづいていますが、なんとかこれ以上「コノフィツム」を枯らすことなく、育てていきたいです。
たね蒔きから515日後(2025年4月2日)
たね蒔きから、515日が経過しました。
-1024x768.jpg)
相変わらず、株同士が押し合う様子が確認できますが、調子を崩す株は見られず、順調な成長をつづけています
まだまだ大人の「コノフィツム」のすがたではありませんが、表面に模様があらわれてきた株もあり、それぞれに特徴があらわれはじめました
(更新中)
自宅で育てている多肉植物(実生)の成長記録は、以下の記事でまとめています
よろしければ、あわせてお読みください
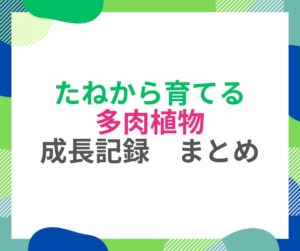
冬型メセン「コノフィツム」の育成環境(たね蒔きから1~2か月経過後)
「コノフィツム」のたねを蒔いた環境は、前述の通りです。
発芽から1~2か月ほど経過してから、育成環境を変えているため、ここでは変更後の環境についてご紹介します
日当たり
「コノフィツム」は夏に照り付ける強い直射日光は避け、それ以外の季節はよく日に当てることで、健康的な成長を見せる植物です。
光が強すぎると溶けるように枯れてしまい、弱すぎても、ヒョロヒョロとしたすがたに徒長してしまいます。
自宅では、実生1年目の冬のあいだは、毎日10時間、植物育成用のLEDライトを当てていました。
最低気温が10℃以上になってからは、直射日光が3~4時間当たる屋外で育成しています。
最高気温が30℃程度になってからは、屋外の日陰に置き、強い光を避けながら育てています。
光が強い場所に移動する場合は、一気に環境を変えると、「コノフィツム」にストレスを与えてしまうことに…。
徐々に環境に慣らしていくことで、環境の変化によるストレスを、最小限にできるでしょう
水やり
「コノフィツム」は比較的乾燥した環境を好むため、水やりは控えめにすることが望まれます。
ただし発芽したばかりの株には、乾燥した環境に耐えられるほど、十分な体力が備わっていません。
幼苗のうちは水やりを多めにしないと、最悪の場合、水分不足で枯れてしまう原因にも…。
自宅では、ある程度株が大きく成長してからは、腰水をやめて毎日水やりをしていました。
気温が上昇するにつれて徐々に水やりを減らし、夏のあいだは断水気味で育てることで、秋からの成長期に備えています。
冬のあいだに、寒い環境で育てるなら、月に1~2回ほどの水やりにし、「コノフィツム」の耐寒性を上げることが重要です。
実生の場合、水やりを多めにするタイミングから、徐々に水やりを減らすタイミングがむずかしいかもしれません。
水やりの際は、鉢底から水が流れ出てくるまでたっぷりと与えることで、鉢内の環境を入れ替えています。
肥料
「コノフィツム」は栄養分の少ない土壌で暮らしているため、成長のために多くの肥料を必要としません。
特に夏と真冬の季節には、肥料を吸い上げなくなります。
成長期にあたる春と秋の涼しい季節に、少量の肥料を与えることで、健康的な成長を見せるでしょう。
自宅では培養土に固形肥料(緩効性肥料)を配合し、育成しています。
液体肥料は与えていませんが、成長期に液体肥料を与えてもよいでしょう。
コメント