育てやすい観葉植物
ガジュマルの基本データ
育 て 易 さ:★★★★★
成 長 速 度:★★★★☆(枝葉はよく成長するが、幹は肥大しづらい)
入手し易さ:★★★★★
耐 寒 性:★★★★☆(耐寒温度(目安):5℃)
耐 暑 性:★★★★★
原産地:台湾、沖縄、屋久島、種子島
花言葉:たくさんの幸せ、健康
科・属:クワ科・イチジク属
学 名:Ficus microcarpa(フィカス・ミクロカルパ)
別 名:「幸せを呼ぶ木」、「多幸の木」、「タイワンマツ(台湾松)」、「トリマツ(鳥松)」、「精霊の宿る木」、「絞め殺しの木」、「レインツリー(雨の木)」
ガジュマルの成長記録
2020年8月ごろにお迎えした、「ガジュマル(Ficus microcarpa)」の成長記録を付けていきます
2022年12月17日(December 17, 2022)
まずは、記録開始時の「ガジュマル」の様子です。
-2.jpg)
土の上では肥大した根が存在感を発揮し、幹を伸ばした先では、光沢感があり丸みを帯びた葉を展開するのが特徴的です。
メジャーな品種で、100均に並ぶこともある
「ガジュマル」は、ガーデニングショップに足を向けると、必ずと言っていいほど出逢える、メジャーな品種。
今のところ100円ショップでは、税込330円の「ガジュマル」しか見たことがありませんが、税込110円で売られていることもあるようです。
すがたは多岐にわたり、サイズ感もさまざま
観葉植物は、おもに“葉”を“観”て楽しむ植物ですが、「ガジュマル」は葉だけではなく、大きく成長する“根”も楽しめる品種。
肥大する根のカタチは、株ごとに異なり、バリエーションが豊かです。
ガーデニングショップに足を運ぶと、「ガジュマル」がいくつも置かれている光景を目にすることも多いです。
その中から、自分が好きなカタチをした「ガジュマル」を見つけ出すのも、楽しみ方のひとつ!
園芸として楽しまれている「ガジュマル」は、鉢相応のサイズに仕立てられています。
その一方で、沖縄などの温暖な地域では、樹高が30m近くまで成長する、大迫力な「ガジュマル」も存在します!
③.jpg)
気根(きこん)の量が多い
上の写真に映る植物は、沖縄の自然の中で育つ「ガジュマル」。
幹から下に垂れ下げている気根(きこん)の数は、100本ほどあるのではないでしょうか。
その気根の太さにも、目を見張るものがあります!
塊根(かいこん)植物の仲間ではない
根や茎の部分を肥大させる植物に、「塊根(かいこん)植物」と呼ばれる植物がいます。
マダガスカルや南アフリカなどの乾燥地帯を原産地とし、体内に多くの水分を蓄えている植物です。
「ガジュマル」も根を肥大させるので、この塊根植物の仲間だと思われることもあります。
ただし、塊根植物は“多肉植物”の中で根を肥大させる植物ですが、「ガジュマル」は“多肉植物”の仲間ではないので、塊根植物ではありません。
省スペースでも楽しめる
「ガジュマル」は成長速度が早く、枝をドンドン伸ばし、たくさんの葉を展開します
元気よく育つと縦にも横にも成長しますが、定期的に剪定をすることで、コンパクトなサイズのまま楽しめる植物です。
暖かい季節であれば、枝葉を剪定しても調子を崩すリスクが低いため、伸びた枝葉を剪定し、自分好みの樹形に仕立てることもできます!
ガジュマルコバチと共生関係にある
一般的に植物の「受粉」は、自然に吹く風や、不特定多数の虫や鳥が花粉を運ぶことで成り立つもの。
しかし、「ガジュマル」は風などでは受粉しません。
ガジュマルは、このガジュマルコバチを育てるために、特別なお花をつくり、共生関係を結んでいるのだとか!
お互いの存在がなくてはならない、Win-Winの関係が、自然の中でも築き上げているのです。
2024年4月3日(April 3, 2024)
前回の記録から、約1年4か月後の「ガジュマル」の様子です。
「ガジュマル」は常緑樹なので、基本的に葉を一斉に落とすことはありませんが、落葉が進み、葉の数が少なくなってしまいました…。
①-1-768x1024.jpg)
まだ完全に枯れてはいませんが、このままの状態では、枯れてしまうリスクもあります…。
落葉した原因
落葉した原因は、おそらく下記の3点。
- 水の与えなさ過ぎ
- 根腐れ防止のために、冬のあいだは、水やりを控えめにしている
- 日照不足
- 根詰まりを起こしている
- 鉢内が根でギュウギュウになり、水や肥料分を、吸い上げられていない
水やりを減らすことで、寒さに強くなるので、「ガジュマル」の耐寒性の面でも、冬は水やりは控えめにしていました。
植え替えの適期を迎えている
いくつか考えられる原因のうち、特に、根詰まりの可能性が高いと思います。
気づけば、もう4年弱も植え替えをしていません…。
観葉植物の植え替えが必要なタイミングは『鉢底穴から、植物の根がはみ出てきたタイミング』が、ひとつの目安です。
自宅で育てている「ガジュマル」の根は、鉢の下から出てきているので、植え替えのタイミングを迎えているようです。
-1024x768.jpg)
びっしりです…。
ガジュマルの“丸坊主”
このあと、体調回復のために「ガジュマル」の枝を根元から落とす『丸坊主』(まるぼうず)を行いました!
下記の記事で、丸坊主のメリットや用意するものなどについて、詳しくご紹介しています
ご興味があれば、あわせてお読みください
ゴムの木の仲間で、樹液には注意が必要
ガジュマル(ゴムの木)の樹液には、ゴムの材料となる、“ラテックス”という成分が含まれています。
肌が弱いひとがこの樹液に触れると、かぶれることがあるので、剪定をする際は手袋をつけた方が無難です。
丸坊主にする際も、樹液に触れる可能性があるので、軍手や園芸用の手袋をはめると安心です。
2024年8月15日(August 15, 2024)
前回の記録から、約4か月が経過しました。
季節は、お盆を迎えています。
-768x1024.jpg)
4月に調子を崩し、落葉していたことは感じさせないぐらい、体調が回復したようです!
『丸坊主』の際にすべて切り落とした枝も、すっかり元通りになりました!
ここまで復活したということは、根も成長しているはずだと思い、なにげなく鉢の下をのぞいてみると…。
①-768x1024.jpg)
2~3か月前に、根をバッサリと切り落としたのですが、切る前と同じ状況になっています
「ガジュマル」を育てるときは、少し大きめな鉢に植えることで、植え替えの頻度を減らせるでしょう。
土の上に置くだけの観葉植物専用の肥料
土の上に置くタイプの肥料を使用することで、植え替えをせずに追肥を与えることができます。
以下のものは、肥料のメーカーとして知名度のあるハイポネックスから、観葉植物専用に市販されているものです。
2025年1月26日(January 26, 2025)
前回の記録から、約5か月が経過しました。
記録開始時からだと、2年以上が経過しています。
-768x1024.jpg)
前回の記録時から比べると、葉の数が半分ぐらいに減りました…。
また、鉢の横から見ても、鉢底から根があふれ出ている様子が確認できます。
落葉が進み、株に元気がなさそうな原因は、おそらく前回と一緒です。
ただし、小さな鉢に植わっている「ガジュマル」が好きなので、次の植え替え時には、根をもっとバッサリと整理してもよいのかもしれません。
(更新中)
自宅では、他にも観葉植物を育てています。
品種ごとの成長記録&育て方は、下記の記事でまとめているので、よろしければチェックしてみてください
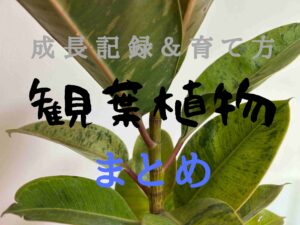
ガジュマルの育成環境
「ガジュマル」はとても丈夫で育てやすいので、はじめて育てる植物としてもオススメです!
日当たり
「ガジュマル」は沖縄などで自生している植物なので、暑さには強く、寒さには弱い特徴をもっています。
太陽の光が好きなため、直射日光にも強いですが、耐陰性(たいいんせい)があるので、多少暗い場所でも育てられます。
明るさの目安は、昼間に照明をつけなくても、不都合なく本を読めるかどうか。
読書ができるほどの明るさがあれば、耐陰性のある植物は、生きていけると言われています。
自宅では、春から秋までは、午前中から日没まで直射日光が当たる場所に置いています。
季節によって変動はあるものの、1日の日照時間を平均すると、約4~5時間です。
冬は、植物育成用LEDライトが、遠くから当たる環境で育てています。
耐寒温度は5℃とされていますが、自宅では安全をみて、最低気温が10℃を下回ってきたタイミングで、室内に取り込んでいます。
「ガジュマル」は日照が足りないと、枝葉がヒョロヒョロと徒長してしまうことも…。
株が徒長した場合は、枝葉を剪定し、樹形を整える必要があるでしょう。
日照条件が過度に悪い環境では、枝葉を落としてしまうこともあります。
完全に落葉したとしても、そこから復活することもあるので、日照時間を改善して様子をみることが必要です。
特に、「ガジュマル」の幹が硬い場合には、復活する可能性が残されています!
水やり
「ガジュマル」は乾燥に強いので、多少の水切れを起こしても、すぐに枯れるわけではありません。
表土が乾いたら、たっぷりと水やりをすることが、基本的な育て方です。
自宅では、春から秋までは表土が乾いたら、鉢底から流れ出てくるまで水やりをしています。
冬は、1か月に2~3回ほどの頻度で水を与えています。
暖かい環境を保てるのであれば、必要に応じて、水やりの頻度を高くすることが望まれるでしょう。
たっぷりと水やりをすることで、雑菌などを洗い流すことができ、鉢内の空気も水圧によって入れ替えることができます。
霧吹きなどで葉に水をかける葉水(はみず)は、「ガジュマル」が本来暮らしている、湿度の高い環境に近づけることができるもの。
自宅では冬は乾燥対策として、なるべく毎日、葉水を行っています。
100円ショップで入手できる霧吹きの中で、ミストを出せるものが販売されています。
下記の記事で詳しくご紹介しているので、よろしければお読みください。
肥料
「ガジュマル」は、肥料が好きな植物です。
成長期である春と秋に、肥料を与えることで、健康的に育てることができるでしょう。
自宅では元肥の入っている市販の『観葉植物の土』に植え、春と秋には、2週間に1度ほどの頻度で液体肥料を与えています。
液体肥料を使用する場合は、「観葉植物」と記載されている項目に合わせて希釈し、使用することで、肥料で失敗するリスクを軽減させることができます。
数年間植え替えていない場合は、土の中の肥料が不足している状態に…。
追加で肥料を与えるか、肥料の含まれている土に植え替えて、「ガジュマル」が肥料を吸い上げられる環境を準備することが重要です。
「ガジュマル」は、寒い季節や暑さがピークに達する期間は、ほとんど肥料分を必要としません。
季節に応じた、肥料の管理が必要です。
コメント