この記事は「【保存版】多肉植物にまつわる専門用語まとめ(後編)~タニラー用の辞典~」の後編です
多肉植物にまつわる専門用語のア~ナ行については、以下の記事で解説しています

.jpg) 筆者
筆者専門用語を知っておけば、さらに多肉植物を楽しめるかもしれません。
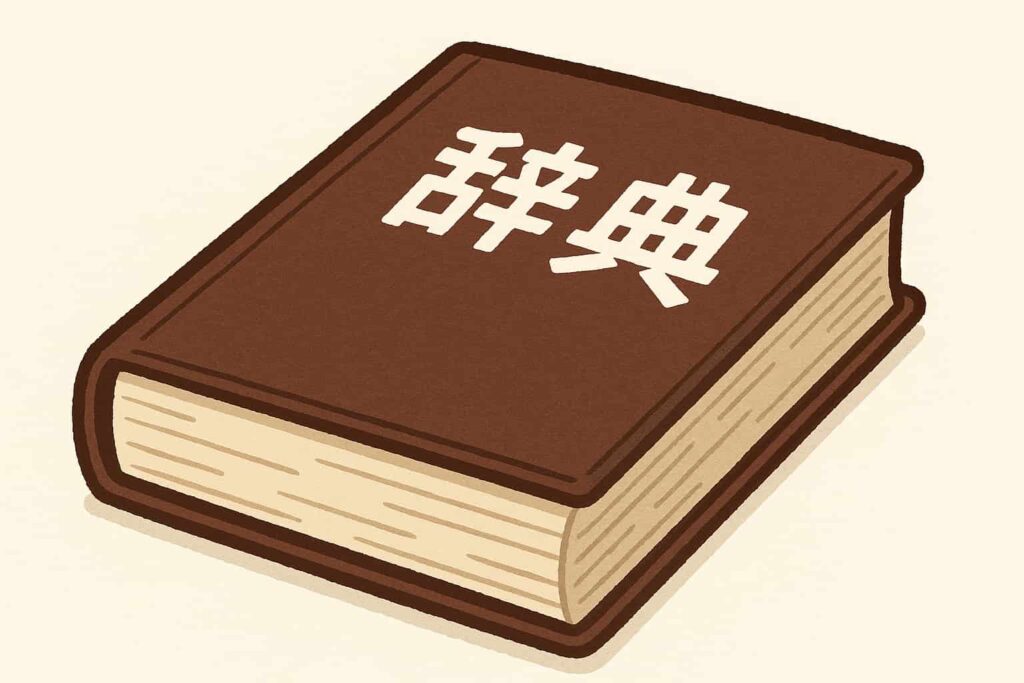
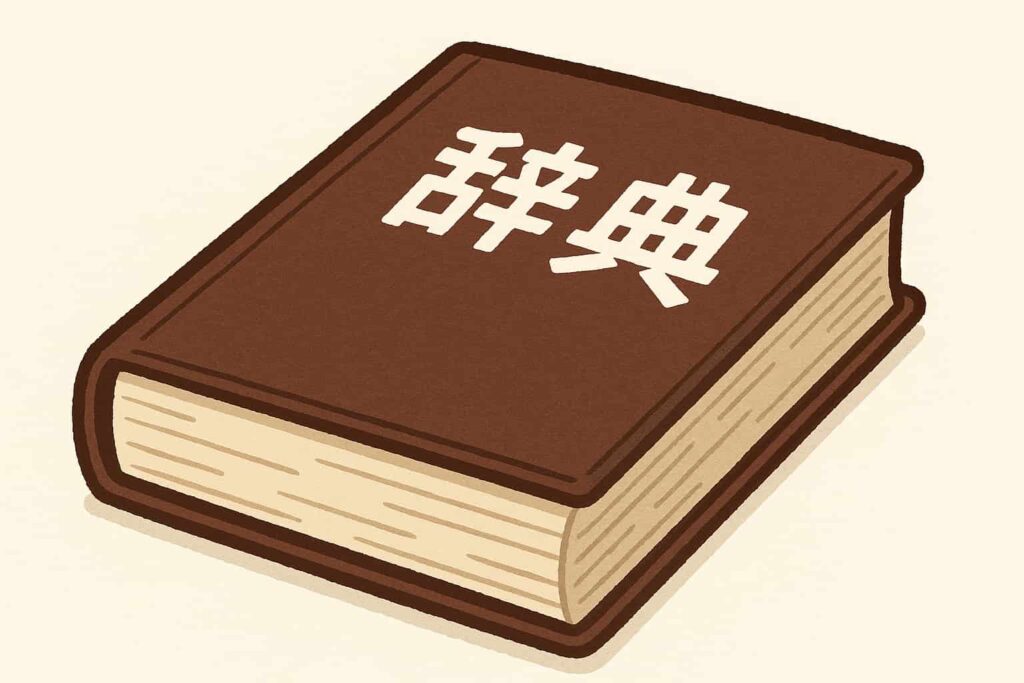
多肉植物にまつわる専門用語
ハ行 ~ ワ行
ハ行
ハオ (はお) :ハオルチア属の植物を略した呼び方です。
ハイブリッド種(hyd):異なる品種を交配し、生まれたあたらしい品種のことです。
たとえば病気に強い品種「A」と、花がうつくしい「B」をかけ合わせることで、病気に強く、うつくしい花を咲かせる植物が生まれる可能性があります。
(対義語・反対語:純血種)
パキポ:パキポディウム属の植物を略した呼び方です。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
パキポディウム属の「グラキリス」は、塊根植物の中でも特に人気が高い品種です。
培養土(ばいようど):複数の基本用土や補助用土を配合し、植物育成に必要な成分をバランスよく調整した土のことを指します。
市販されている「多肉植物の土」や「観葉植物の土」などは、それぞれの植物に適した培養土の一種です。
(対義語・反対語:基本用土、補助用土)
葉挿し (はざし):多肉植物を増やすための手法のひとつで、ちぎった葉から根を出させ、あらたな個体にすることです。
おもにエケベリアやグラプトペタルム、グラプトベリアで用いられ、葉のつけ根からきれいに外せると成功率が高まります。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
葉挿しの成功率が高い品種は、どんどん増やせます。
鉢上げ(はちあげ):育苗トレーなどで発芽したばかりの幼苗を、本格的な栽培用の鉢に植え替える作業のことです。
鉢底穴(はちぞこあな):植木鉢の底にある、水を抜くための穴のことです。
鉢底穴がない鉢や、装飾用の鉢カバーには自分で穴を開ける必要があります。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
苔テラリウムを育てるビンなど、穴が開けられないものは、霧吹きを使うなど、水やりを少量に抑える必要があります。
鉢底網(はちぞこあみ):鉢の底に敷く網のことです。
土がこぼれるのを防ぐだけでなく、ナメクジなどの害虫が、鉢底穴から侵入するのを防ぐ効果もあります。
鉢底石(はちぞこいし):鉢の底に敷いて、水はけや風通しをよくするための石です。
水はけがよい土を使ったり、スリット鉢を使ったりする場合は、鉢底石は必要ありません。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
スリット鉢に鉢底石を敷くと、スリット鉢の本来のメリットを半減させてしまいます。
スリット鉢については、以下の記事で解説しています
鉢増し(はちまし):これまで使っていた鉢よりひと回り大きな鉢に、植物を植え替えることです。
根が成長できるスペースを広げることで、植物の成長を促す目的で行われます。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
定期的に鉢増しをすると、育成スペースが圧迫される原因にも…。
植え替えの際に根を整理し、元々の鉢に植え戻すことで、植物をコンパクトなまま育てられます。
発根(はっこん):植物が根を生やすことです。
根が生えるように手助けすることを、「発根管理」と言います。
- 発根株
- 根が生えた株
- 未発根株に比べ、高額な価格帯で取り引きされる
- 未発根株
- 根が生えていない株
- 発根株に比べ、安価な価格帯で取り引きされる
- 根が生えず、そのまま枯れてしまうリスクもある
.jpg)
.jpg)
.jpg)
‟塊根植物の王さま”と言われる「オペルクリカリア・パキプス」が発根する確率は、1~2割と低めです。
未発根株を入手する場合は、リスクを理解した上で、お迎えするようにしましょう。
アガベの発根管理については、以下の記事でコツを解説しています
発根促進剤(はっこんそくしんざい):植物の発根を促す目的で使われる薬剤です。
未発根株を管理する際や、挿し木であたらしい株を増やす際に役立ちます。
- ルートン
- オキシベロン
「ルートン」はリーズナブルなため、挿し木をする際に、お試し感覚で使ってみてもよいかもしれません。
ちなみに、発根を促進する目的で「メネデール水溶液」が用いられることもありますが、「メネデール」には植物を発根させる効果はありません。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
発根した‟芽”や‟根”が‟出る”ことから、「メネデール」と名付けられています。
葉水(はみず):植物の葉に、霧吹きで直接水をかけることです。
高い湿度を好む観葉植物の乾燥対策として行いますが、多肉植物は乾燥に強いため、基本的に「葉水」は必要ありません。
ただし、多肉植物を冬の乾燥した室内で管理する際には、補助的に「葉水」を行うこともあります。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
植物が葉から取り込める水分量は多くありませんが、葉水を行うことで、土を濡らさずに植物に吸水できます。
「葉水」については、以下の記事で100円ショップのアイテムをご紹介しているため、ご興味があればお読みください
葉焼け(はやけ):強すぎる光が原因で、植物の葉が焼けてしまうことです。
植物が「葉焼け」を起こしやすくなる原因は以下のとおりです。
- 直射日光を長時間当てたり、植物育成用LEDライトを至近距離から照射したりする
- 日陰で管理していた植物を、急に日当たりのよい場所に移動する
- 風通しが悪く、気温が高い環境で植物を育てる
.jpg)
.jpg)
.jpg)
近年は地球温暖化が進み、植物が葉焼けを起こすことが増えています。
遮光ネットや寒冷紗を活用することで、日照量を調整しましょう。
春秋型(はるあきがた):春や秋の暖かく、過ごしやすい気候でよく育つ植物のグループのことです。
暑すぎる夏や寒すぎる冬には、成長が停滞します。
半日陰(はんひかげ):木漏れ日ほどの日が当たる環境のことです。
一般的には、50%ほど光が遮られる環境を指しますが、直射日光が2~3時間当たる場所を指すこともあります。
バンカープランツ:害虫を食べてくれる「肉食の虫」をおびき寄せる植物のことです。
B面(ビーめん):植物を360度回して見たときに、もっとも魅力的に感じる「A面」の、ちょうど反対側にあたる面のことです。
(対義語・反対語:A面)
ビザールプランツ:風変わりなすがたをした「珍奇(ちんき)植物」のことを指します。
微発根(びはっこん):それまで根がなかった植物に、あたらしく生えてきたばかりの短い根のことです。
微発根の植物を「微発根株」と言います。
(同義語:ちょろ根)
肥料焼け:植物に与える肥料の量が多すぎたり、与える時期を間違えたりすることで起こるトラブルです。
特に、植物の成長が停滞したり暑すぎる季節に施肥したりすると、肥料焼けの原因になります。
斑入り (ふいり) :葉に緑色以外の色が混じる現象、またはその植物を指す言葉です。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
斑入りの品種は、ユニークな見た目から、観賞用の植物として人気があります。
普及種(ふきゅうしゅ):流通量が多く、比較的カンタンに入手できる植物のことです。
- 万人受けする見た目
- よく増える
- 挿し木の成功率が高い、次々に花を咲かせて種子を付ける など
- 調子を崩しにくい
- 寒さや暑さに強い、加湿や乾燥に強い など
覆土(ふくど):用土を上からかけることを意味し、おもに種を蒔く際に使われる言葉です。
発芽するために光を必要としない「嫌光性種子」の発芽を促すため、光を遮る目的で行われます。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
水分や温度を保ったり、風で種子が飛んでいくのを防止したりするのも、種子に覆土する目的です。
覆輪(ふくりん):葉や花の縁に、斑が入ることです。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
覆輪斑(ふくりんふ)と表現されることもあります。
不織布(ふしょくふ):植物を保護するために使われるシート状の資材です。
おもな用途は、虫よけや冬の寒さ対策で、園芸店以外に100円ショップでも手に入ります。
分頭(ぶんとう):もともと1つだった植物の成長点が2つ以上に分かれ、成長していく現象のことです。
札落ち (ふだおち) :育成過程の中で、園芸ラベルが紛失し、品種名が特定できなくなった植物を指す言葉です。
札落ちの植物は通常よりも、手頃な価格で取り引きされる傾向があります。
「sp.(エスピー)」も品種名が分からない植物のことですが、「sp.」が学術的に使われるのに対し、「札落ち」は園芸的に使われる言葉です。
冬型 (ふゆがた) :寒い気候でよく育つ植物のグループのことです。
ただし「冬型」の植物が自生する地域は、厳しい氷点下まで気温が低下することは、ほとんどありません。
「冬型」の植物でも、寒すぎる環境で生育するのはむずかしく、5~20℃ほどのすずしい環境を好む品種が多いです。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
冬型の植物は、暑い季節に休眠します。
ブロメリア:ブロメリア科(パイナップル科)に属する植物のことです。
ブロメリアの代表的な品種には、ディッキアや、生育に土を必要としない「チランジア(エアプランツ)」がいます。
ベアルート:根に付いた土を、すべて落とした状態のことです。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
土を落とした植物のことを、ベアルート株と呼びます。
病害虫が他の国に広がらないように、「植物の根を切り落とした上で輸出入する」という国際的なルールがあるため、「ベアルート株」が出回ります。
ベニカ:植物の害虫や病気の対策として、広く使われているスプレータイプの殺虫・殺菌剤です。
ひとつ持っておけば、いざというときの急なトラブルにもすぐ対処できます。
pH(ペーハー、ピーエッチ):土の酸性・アルカリ性の度合いを示す言葉です。
植物の生育には、植物ごとの自生地の「pH」が、理想的とされています。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
pHが多少合わなくても、すぐに枯れることはありませんが、pHを整えることで元気に育ちやすくなります。
変種(へんしゅ):同じ植物の品種でありながら、他の株とは異なる特別な特徴(葉の色合いや形状など)をもつものを指します。
穂木(ほぎ):接ぎ木で使われる、台木の上に乗せる植物のことです。
成長速度が遅かったり、病気に弱かったりする植物を、丈夫な台木の力で元気に育てます。
(対義語・反対語:台木)
補助用土(ほじょようど):土の性能をアップさせるための「調整役」の用土です。
保水性を高めたいなら「ピートモス」、水はけをよくしたいなら「パーライト」といったように、目的に合わせて基本用土に加えることで、より健康な植物を育てることができます。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
バーミキュライトやくん炭なども、多肉植物の培養土に使われることが多い補助用土です。
自宅で使用している培養土の配合割合については、以下の記事で解説しています


マ行
窓(まど):ハオルチアの葉の先端にある、光が透過する部分のことです。
この「窓」から光を取り込むことで、葉の内部にまで光を届け、光合成を助ける役割を担っています。
間延び(まのび):植物が光を求めて、茎を無理に伸ばそうとすることで起こる現象です。
日当たりの悪い場所で育てると、葉や茎が不健康に間延びし、全体的に弱々しい印象になってしまいます。
(同義語=徒長(とちょう))
幹上がり・幹立ち(みきあがり・みきだち):本来アロエやアガベなどは、ロゼット状に葉を展開するため、茎や幹がほとんど見えません。
そのような植物が幹を伸ばし、立ち上がったすがたに成長することを「幹上がり」や「幹立ち」と言います。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
幹の先に葉が生い茂る、樹木のような見た目になることです。
実生(みしょう):種子から発芽させて、植物を育てることです。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
種子から育てた植物自体を「実生株」と言います。
日本で育った実生株は、海外から輸入した植物と比べて日本の気候に順応しやすく、育てやすい傾向があります。
(対義語・反対語:現地球)
多肉植物の種子を蒔く方法は、以下の記事で解説しています
微塵(みじん):土が砕けてできた、きわめて細かい粒子のことです。
「微塵」が多いと、土の隙間が埋まってしまい、通気性や水はけを劣化させる原因になります。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
園芸用のふるいを用いると、微塵を取り除くことができます。
水切れ(みずぎれ):土がカラカラに乾燥したり、植物が蓄えている水分が足りなくなったりした状態のことです。
乾燥に強い多肉植物でも、水がなければ、いずれ枯れてしまいます。
水切れを起こした多肉植物は、萎れたり、葉や幹にシワが入ったりします。
通常は水やりをすれば改善されますが、水切れが深刻な場合は、水を溜めた容器に鉢ごと30分ほど浸ける方法も有効です。
未発根株(みはっこんかぶ):根が生えていない植物のことです。
(対義語・反対語:発根株)
雌株(めかぶ):植物の中には、性別が分かれている品種がいます。
そのうちメス(♀)の役割を持つ株を「雌株」と呼び、種子をつくるために、オス(♂)の花粉を受け取る役割を担っています。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
読み方は、「めすかぶ」ではなく「めかぶ」です。
雌花(めばな):雌しべだけがあって、雄しべがないか、発達しない花のことです。
雌花が受粉することで、植物は実を結び、種子を付けることができます。
メリクロン:植物の成長点から、元の植物とまったく同じ性質をもつ個体を、大量につくり出す人工的な繁殖方法です。
この技術によって増えた植物を「メリクロン株」と言います。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
植物を増やす方法はいくつもありますが、一気に多くの株数を増やせるのがメリクロンです。
木質化(もくしつか):植物の茎や幹が、緑色から茶色く変色し、硬くなる現象のことです。
この状態が進んだ植物は、より風格のある見た目になり、希少性や価値が高まる傾向にあります。
元肥(もとごえ):植物の生育初期に必要な栄養を補給するため、植え付けの際に土に混ぜておく肥料のことです。
土づくりの段階でしっかり与えておくことで、植物が根を張り、元気に育つための基礎がつくれます。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
“もとひ”と呼ばれることもありますが、正確には“もとごえ”です。
モンスト:植物の成長点が乱れ、平らな帯状になることです。
植物の奇形の一種として知られています。
(同義語:石化)
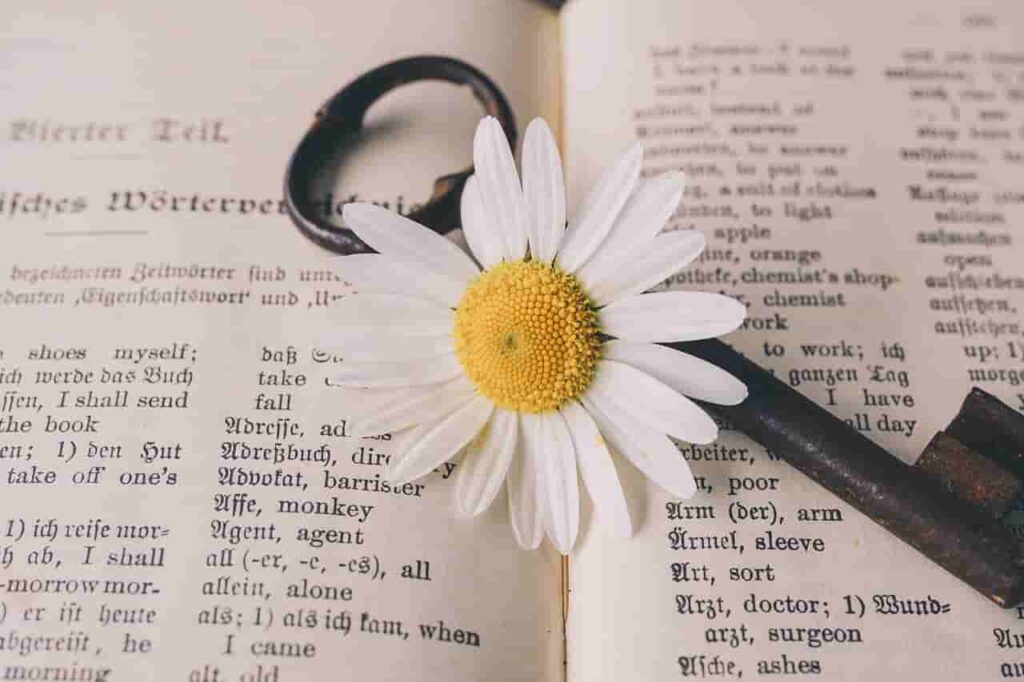
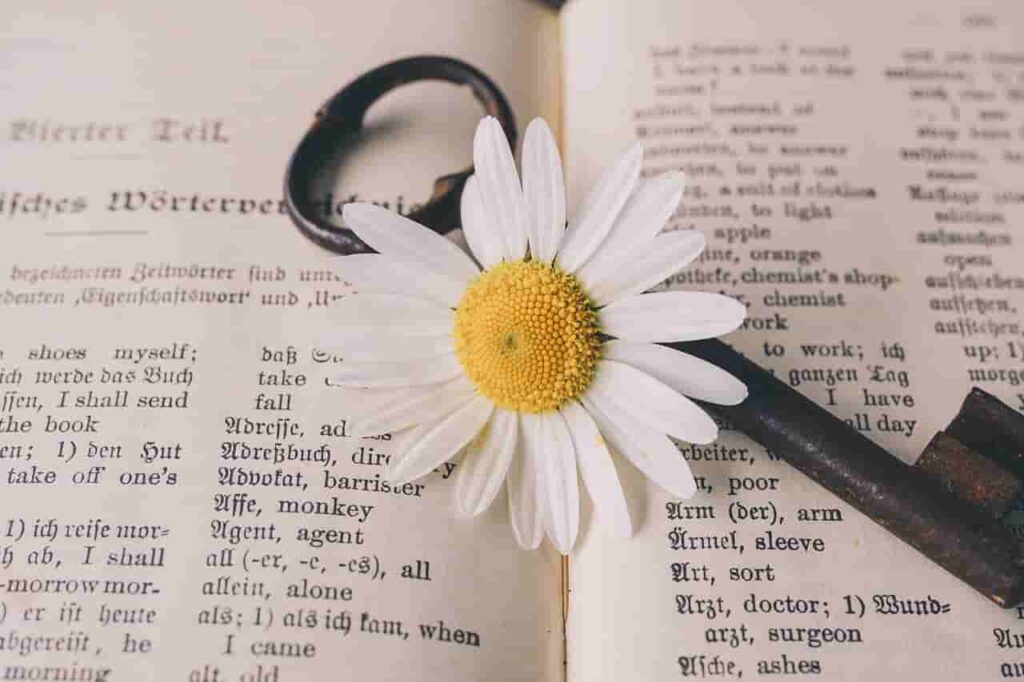
ヤ行
ユーフォ:ユーフォルビア属の植物を略した呼び方です。
ユーフォルビア属の植物は根張りが弱い品種が多いため、植え替えの際は、過度に根を整理しない方が元気に育ちます。
寄せ植え(よせうえ) :ひとつの鉢に、複数の植物を植えることです。
さまざまな植物を組み合わせることで、植物の見た目をさらに引き立たせる手法です。
見た目が華やかになる一方で、植物同士が根を伸ばすスペースが限られるため、成長速度が遅くなることもあります。
しかし、周囲の植物との適度な競争が、植物を丈夫に育てるという考え方もあります。
葉縁(ようえん):葉の縁(周り)の部分のことです。
ラ行
ランナー:植物が茎を長く伸ばし、その先に子株を付けることがあります。
そのときに伸ばした茎のことを「ランナー」と言います。
稜(りょう):サボテンの表面にある、縦方向の出っ張ったヒダのことです。
多くのサボテンを特徴づけるトゲは、この稜に沿って生えます。
連棘 (れんし) :複数のトゲ(鋸歯)が連なっていることです。
ロゼット:茎がほとんど伸長せずに、葉がバラの花のように地面に広がるすがたのことです。
エケベリアやアガベが、葉を展開させるようなすがたを表現するときに用いられます。
ワ行
矮性(わいせい):同じ品種の他の株と比べて、コンパクトなすがたを維持する植物のことです。
一般的には、名前に“コンパクタ”や“姫”と付いている植物も、他の株より小型に成長します。
脇芽(わきめ):茎や葉の付け根から出る、あたらしい芽のことです。
まとめ
前編と合わせることで、多肉植物の「ア」から「ワ」まで、すべての専門用語を網羅できたことになります。
専門用語の数々は、多肉植物を育てる上で、必須の知識ではありません。
この記事が、あなたの多肉植物ライフを豊かにする手助けとなれば幸いです。
用語を正しく理解し、ぜひ今後の育成に役立ててください。
以下の記事では、ひとりでも没頭できる「園芸」の魅力をご紹介しています
よろしければ、あわせてお読みください


コメント