元気よく育てるために
植物と暮らしていると、ふとした瞬間に「いつもと様子が違うかも?」と感じることはありませんか?
- 植物の葉が萎れている
- 植物の葉が黄色や茶色く変色している
- 去年は花を咲かせたが、今年は咲かせない
植物は言葉を話せない代わりに、見た目や成長の変化を通じて、体調不良を伝えてくれています。
そうしたサインを見逃さず、適切に対応することが、植物と長く付き合う上でとても大切です。
植物が元気に育つためには「光・水・風・温度・栄養分(肥料分)」の5つのバランスが欠かせません。
ひとつでも条件が崩れると、体調を崩し、最悪の場合は枯れるリスクを高めてしまいます。
原因を知ることは、植物を守る第一歩
大切な植物の健康を守り、豊かなグリーンライフを送るために必要なヒントが詰まっているため、ぜひお読みください
植物が成長するための「5つの要素」
まずは、植物が成長するための要素について、確認しておきます。
植物が元気に成長するためには、以下の「5つの要素」が特に重要です。
- 光
- 水
- 風
- 温度
- 栄養分(肥料分)

植物にとって「5つの要素」が過ごしやすい程度に保たれていれば、植物は元気に暮らすことができます。
ただし、このうち1つでも過剰になったり不足したりすると、植物が体調を崩すこともあるでしょう。
観葉植物&多肉植物が「枯れる」11個の原因
日当たり
日照不足
植物は太陽から降りそそぐ光をつかい、生きていくためのエネルギーをつくり出しています。
長期間そのような環境で過ごすと、エネルギー不足に陥り、やがて枯れてしまうでしょう。
日が強すぎる
必ずしも強い光に長い時間当たればよいのではなく、一日に植物が光合成できる量には、限界があります。
植物がエネルギーに変換できないほど多くの光を浴びると、調子を崩してしまう原因にも…。
最近市販されている植物育成用のLEDライトは、照射距離を近くすれば、かなり強い光を生み出せます。
強い光を当てて、植物の成長をさらに促そう!
日当たりへの対策
具体的な対策は、いくつかの方法があります。
- 品種ごとの望ましい日照量を把握する
- ガーデニング用品を活用する
- 植物の調子が悪い場合は、日照量を減らす
品種ごとの望ましい日照量を把握する
植物の品種によって、望ましい日照量は異なります。
- 強い光が好きな植物
- サボテン・アガベ など
- そこまで多くの光量を必要としない植物
- 観葉植物・苔 など
品種ごとに必要な光量を把握できないと、望ましい育成環境が分かりません。
ガーデニング用品を活用する
日照量を調整するガーデニング用品を、必要に応じて活用することも対策のひとつです。
- 遮光ネット、寒冷紗
- 強すぎる光を調整したいときに使用すると、日照量などを弱められる
- 植物育成用のLEDライト、反射シート
- 強い光を確保したいときに使用すると、多くの光量を確保できる
- LEDライトは、光量だけではなく照射時間も変更できるため、必要な光量を確保しやすい
植物の調子が悪い場合は、日照量を減らす
植物が調子を崩している場合は、日陰に移動するなど、普段よりも日照量を減らすことが重要です。

風通し
強い風が当たりすぎる
植物が成長するためには、ある程度の風通しが必要です。
台風時などには鉢が転倒したり、枝や幹が折れたりするリスクもあります。
風通しが悪い
風通しが悪い環境では、いつまでも土が乾かなくなり、土の中に菌が繁殖する原因にも…。
冬や梅雨どきなどに、いつまでも洗濯物が乾かないと菌が繁殖し、生乾きの臭いが生じるのと同じ原理です。
さらに風通しの悪さは、以下のような影響も与えます。
- 害虫が発生しやすくなる
- 葉や茎が乾きづらくなり、乾燥した環境を嫌う害虫を寄せ付けやすくなる
- 光合成の効率が下がる
- 光合成に必要な二酸化炭素が供給されにくくなる
- 貧弱な株に成長する
- 刺激がないと、幹や枝葉が丈夫に成長しにくい
- 体温を調整しづらくなる
- 植物は葉から水分を蒸散させることで、体温を調整しているが、風通しが悪いと水分が蒸発しにくくなる
風通しへの対策
風が強すぎる場合
風が強すぎる場合は、物陰や建物の壁沿いに鉢を移動することで、風からの影響を弱められます。
場所を移動できない場合は、空の鉢や他に育てている植物の後ろに移動するだけでも、風の影響を軽減させられます。
風通しが悪い場合
サーキュレーターを使用する場合は、直接風を当てると、植物を必要以上に乾燥させてしまいます。
植物には直接風を当てず、室内の空気を循環させるように使用するのが望ましいです。
サーキュレーターよりも扇風機の方が機械が大きいため、効率的に空気の流れをつくり出せるのではないか?
と思われる方もいるでしょう。
ですがサーキュレーターの方が、遠くまで空気を送り込む能力に長けています。
サーキュレーターは、多くの機能があり、製品ごとに販売価格もさまざまです。
- 首振り機能(360度回転可能なものも)
- 自動停止機能
- 風量調整機能
サーキュレーターの使用以外にも、風通しの対策方法はいくつかあります。
- 鉢の間隔を空ける
- 剪定する
- 支柱を利用する
- つる性の植物に有効な方法
水やり
水やりの難易度は高い
多くの植物にとって、「土が乾いてから水やりをする」のが、理想的な水やり頻度です。
単純な作業に見えますが、なぜ水やりの習得に時間が必要なのかというと、さまざまな要素が挙げられます。
まずは、品種ごとの性質の面。
どの程度の水やりが必要かどうかは、植物によって異なります。
- 湿度が高い環境が好きで、乾燥した環境は苦手
- 観葉植物 など
- 乾燥気味な環境の方が健康的に育つ
- サボテン など
さらに以下のように、植物を取りまく環境はそれぞれ異なり、「週に●回与える」という明確な頻度が定めにくい点も、難易度が高い要因です。
- 土の乾き具合を判断するのがむずかしい
- 土の中まで乾いているかどうか、見た目では分かりづらい
- 鉢の材質や大きさ、培養土の性質によっても乾燥する速度に影響が出る
- 季節や環境によって、水やりを調整する必要がある
- 温度や湿度、日当たりなどの影響で、適切な水やり頻度は変わってくる
- 植物が水を欲しているのか、正確に把握する必要がある
- 土が乾燥していても、すぐに水やりをする必要がないこともある
植物の「水やり」については、以下の記事で詳しく解説しているので、ご興味があればお読みください
水を与えすぎている
観葉植物の多くは、ジャングルのような湿度の高い場所で自生しているため、乾燥した環境に強くありません。
かといって、ずっと濡れた環境では健康的に成長できず、必要以上に水を与えると、根腐れを起こし調子を崩してしまいます。
水分が不足している
サボテンなどの多肉植物は、降水量の少ない地域で自生しているため、乾燥に強いです。
ですが、水がまったく確保できない環境では、生きていくことはできません。
数週間~数か月ほどの期間であれば、水がなくても生き抜けますが、やがて枯れてしまいます。
水やりへの対策
水やりには、いくつかコツがある
水やりについては、園芸の経験を積み重ねる必要がありますが、水のやりどきを把握するためには、いくつか判断材料があります。
- 植物の成長期や休眠期を把握する
- 成長期にはたっぷりと水やりし、休眠期は水やりの頻度を少なくする
- 土の乾き具合を確認する
- 葉が萎れていないか確認する
土が乾いているのか、どうやって確認するの?
と思われる方もいるでしょう。
鉢をもって重さを比べたり、割り箸を用いて確認したりする方法もあります
以下の記事で紹介しているため、ご興味があれば参考にしてみてください
表土に濡れていると色が変わる用土を使用する
また、濡れると色が変わる土を使用すれば、乾いているかどうか判断しやすくなります。
たとえば、「赤玉土」や「鹿沼土」は、濡れているときに色が変わるため、このような用土を表土に使用すると指標になるでしょう。
水やりチェッカーを使用する
また、土の乾き具合を確認できるガーデニング用品を使用することも、ひとつの方法です。
あらかじめ土に刺しておき、濡れているときに色が変わる「水やりチェッカー」を使用すれば、ひと目で水やりのタイミングを把握できます。
霧吹きで水をかける「葉水」も対策のひとつ
観葉植物の乾燥対策には、霧吹きなどで葉を湿らす「葉水」も、水やりを補完する役割を果たします。
葉水に使用できる100円ショップ産の霧吹きについては、以下の記事でご紹介しているので、ご興味があればお読みください
根詰まり
鉢内が植物の根でギュウギュウの状態、いわゆる「根詰まり」を起こすと、根が成長するスペースがなくなるため、植物が調子を崩す原因になります。
また「根詰まり」の状態では、鉢内の排水性や通気性が悪くなり、水分や肥料分をうまく吸いあげられない原因にも…。
根詰まりへの対策
植物を地面に直接植える「地植え」の場合は、土の体積が広い分、根詰まりのリスクをそれほど心配する必要はありません。
定期的に植え替える
ただし植え替えの際に必要以上に根を整理してしまうと、植物が吸水できなくなり、最悪の場合枯れる原因にも…。
植物を大きく成長させたいのか、現状のサイズのまま育てたいのかによって、根を整理する量が決まります。
植え替える場合には、その植物をどのように育てたいのか、今一度確認してみることがオススメです。
適切なサイズの鉢を使用する
小さな鉢を使用すると、鉢内のスペースが限られてくる分、根詰まりを起こしやすくなります。
ただし最初から大きすぎる鉢を選ぶと、土が乾きにくくなり、根腐れを起こすリスクを高めてしまいます。
スリット鉢を使用する
鉢底の側面に切れ目が入っている「スリット鉢」を使用すると、鉢内のスペースを有効活用しやすくなり、植物が根詰まりを起こしづらくなります。
以下の記事で詳しく解説しているため、ご興味があればお読みください
ウイルスなどの病気
植物が病気に感染して調子を崩し、最悪の場合枯れてしまうこともあります。
ウイルスなどの病気の多くは、植物が自ら発症しているわけではなく、他の植物から害虫が運んできたウイルスにより、感染します。
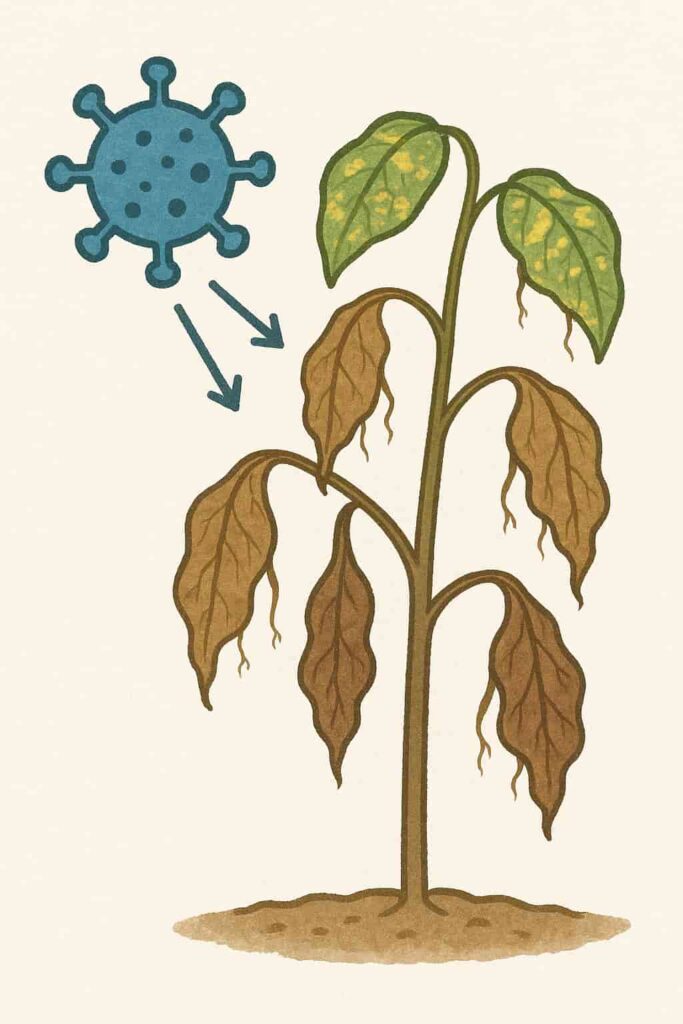
ウイルスなどの病気への対策
植物を元気に保つこと
一度ウイルスに感染してしまうと、傷を負った部分を完治させるのは困難なため、植物を元気な状態に保つことが重要です。
害虫対策のガーデニング用品を使用する
ウイルスを媒介する害虫を防ぐために、ガーデニング用品を使用することも、対策のひとつです。
2022年にアース製薬から、ウイルスの対策ができる「花いとし」が市販されています。
ウイルスだけではなく、殺虫や防虫の効果もあるため、使用できる機会が多い特徴があります。
植物を剪定する際は、園芸用ハサミなどをよく消毒する
ウイルスは剪定の際に、園芸用ハサミなどを伝って、感染するケースもあります。
特に異なる植物を剪定する際は、その都度、剪定用具を殺菌消毒し、ウイルスの感染を防ぎましょう。
害虫&草食動物からの食害
「害虫」は生命力が強くどんどん増殖することから、一度発生すると、根絶させるのはカンタンなことではありません。
樹液を吸ったり葉や茎、根を食べたりする害虫に目を付けられると、美観上の問題では済まないこともあります。
植物枯らしてしまったり、すべての葉を食べつくされたりすることもあるでしょう。
- カイガラムシ
- 葉や茎などから樹液を吸い上げる
- ハダニ
- 葉の裏側から樹液を吸い上げる
- ナメクジ
- 新芽や葉を食べる
- ダンゴムシ
- 根などを食べる
- 枯れ葉を食べて、土に還すありがたい存在でもある
直接的な被害はないものの、「コバエ」は幼虫のあいだ土の中で暮らし、培養土に含まれる有機物を食べてしまいます。
コバエ対策については、以下の記事で詳しくご紹介しているので、ご興味があればご参照ください。
お住まいの地域や環境によっては「ネズミ」や「シカ」などの草食動物が、葉や茎、根などを食べてしまうこともあります。
害虫&草食動物への対策
室内で育成する
害虫は屋外で発生し、いつの間にか植物に付いているケースがほとんどです。
室内で育てられれば、害虫が発生するリスクを最小限に抑えられます。
ガーデニング用品を使用する
他にも、害虫対策のガーデニング用品に頼ることも、選択肢のひとつです。
- 防虫ネット
- 粘着シート
- 光反射シート など
以下の「オルトラン」は、植物の根から殺虫成分を吸収させ、その植物を食べた害虫に効果を発揮する殺虫剤です。
園芸用の殺虫剤として定番で、培養土に配合しておくことで、約1か月効果が持続します。
ただし即効性はないため、すでに害虫が発生している場合は、先ほどご紹介した「花いとし」などのスプレータイプがオススメです。
コンパニオンプランツを活用する
異なる植物を付近に植えることで、防虫の効果が期待できる「コンパニオンプランツ」という対策もあります。
「コンパニオンプランツ」には、相性の良し悪しがあるため、活用する場合は事前に相性を確認する必要があります。
| おもな植物(野菜) | コンパニオンプランツ | 効果 |
|---|---|---|
| トマト・ピーマン | バジル | アブラムシ忌避 |
| ナス | ニラ・ネギ | アブラムシ・ハダニ忌避 |
| キュウリ | ミツバ・シソ | ウリハムシ・アブラムシ忌避 |
| ダイコン | レタス・マリーゴールド | ネキリムシ忌避 |
急激な環境の変化
植物を購入してから、まだあまり時間が経っていないのに、葉が萎れてきた…。
ということは、植物を購入した直後に起きやすい現象です。
植物は地面に根を張っているため、歩いて移動することができません。
場所を移動できる動物と比べると、その場の環境に適応する能力が高いです。
- エアコンが効いた室内から、外気にさらされる屋外に出す
- 雨が当たらない室内から、雨ざらしの場所に移動する
- 日当たりが悪い環境から、直射日光に当たる環境に移動する など
特に季節の変わり目に、植物を枯らしてしまうのが多いのは、急激な環境の変化が生じやすいためです。
植物を購入した直後に調子を崩すのは、環境の変化が原因の場合がほとんどです。
急激な環境の変化への対策
育成環境の違いを把握する
植物を購入する際は、
購入先と自宅では、育成環境が異なる。
ということを、意識する必要があります。
日当たりや温度、風通しにも違いが生じるかもしれません。
環境の変化に徐々に慣らす
育成環境の違いを把握したら、段階的に自宅の育成環境に慣らしていくことで、植物が調子を崩すリスクを最小限に抑えられます。
たとえば直射日光などの強い光が好きな植物でも、もともと日当たりの悪い環境で育てられていたのであれば、いきなり日当たりのがよい場所で育てるのは、リスクを高めてしまいます。
- 1週目
- 室内のレース越しの光が当たる環境で、育てはじめる
- 2週目
- 屋外の日陰に移動する
- 3週目
- 午前中の弱い直射日光が、1~2時間ほど当たる場所に移動する(このような環境を「半日陰」と呼ぶ)
- 4週目以降
- 直射日光のよく当たる場所で育てる
上記の対応は少し過剰かもしれませんが、徐々に環境の変化に慣らすのが無難です。
以下の記事では、季節の変わり目(冬から春にかけて)に、特に気を付けたいポイントをご紹介しています
急激な環境の変化についても詳しく解説しているため、ご興味があればお読みください
気温や湿度が適切ではない
日本のガーデニング業界では、世界中で生息する植物が輸入され、販売されています。
もともとは海外で自生する植物が国内で生産され、今では多くの株数が供給されている植物も、少なくありません。
それぞれの植物で自生地の環境は異なるため、耐寒性や耐暑性は、植物によりさまざまです。
- 自生地の環境が、日本の真冬より厳しい寒さが到来する地域
- 寒さに強く、日本で多少の氷点下にさらされたところで、ビクともしない
- 自生地の環境が、日本の真夏を超えるほどの酷暑が訪れる地域
- 暑さに強く、日本の真夏の直射日光に当てても、葉焼けなどを起こしにくい
日本でたねから育てている「実生(みしょう)」の植物は、ある程度、日本の環境に慣らすことも可能です。
植物の環境への適応力にも限界があるため、耐えられないほどの気温や湿度を感じた場合、調子を崩してしまうでしょう。
気温や湿度への対策
空調が効いた室内で育てる
ビニールハウスでも、ある程度の対策はできます。
デメリットは、室内で育成するためのガーデニング用品を準備する必要があるのと、電気代が発生する点です。
多肉植物に焦点を当てた記事ですが、室内育成については、以下の記事でご紹介しています
水やりを減らすことなどで寒さ対策ができる
寒さへの対策は、いくつか方法がありますが、たとえば以下のようなものが挙げられます。
- 植物に風が直接当たらないようにする
- 水やりを控えめにし、体内の水分量を減らす
- 枯れないように注意が必要
- 二重鉢にする
寒さ対策については、以下の記事で詳しく解説しているため、よろしければ参考にしてみてください
直射日光に当てないことなどで暑さ対策ができる
一方の暑さへの対策にも、以下のような方法があります。
- 直射日光を避ける
- 風通しがよい環境で育てる
- ガーデニング用品の力を借りる
- 遮光ネットなど、100円ショップでも入手可能なアイテムもある
植物の暑さ対策は、以下の記事でご紹介しています
湿度が低い場合は、葉水で対策できる
霧吹きで植物の葉に水をかける「葉水」は、特に、乾燥を嫌う観葉植物に取られる対策のひとつです。
複数の植物を育てている場合は、株同士を近くに置くことでも周辺の湿度を上げられます。
- 鉢の受け皿や園芸用トレーに水を張る
- 加湿器を使用する、濡れたタオルを干す など
湿度が高い場合は、葉水や置き場所に気を付けることで対策できる
湿度が高い環境で、乾燥した環境を好む植物を育てる場合は、雨ざらしの環境を避けることで一定の効果が期待できます。
また、風通しがよい環境で育てることで、土や葉の表面が乾燥しやすくなるため、ジメジメした環境を回避できます。
- 排水性や通気性に優れた培養土に植える
- 除湿器(エアコンの除湿モード)を使用する など
栄養分(肥料分)
栄養分が不足している
植物は、根から肥料分を吸い上げることで、栄養を補給する生き物です。
特に栄養分が多い土壌で暮らす植物が、肥料分が不足した状態で暮らすと、エネルギーが補給できず、やがて枯れてしまうでしょう。
肥料を与えすぎている
肥料を過剰に与えると、植物の根が肥料分によって傷む「肥料焼け」を起こし、調子を崩す原因になります。
特にサボテンなどの多肉植物は、栄養分が少ない土壌で暮らしています。
しばらく肥料を与えなくても枯れるリスクは低く、多くの肥料分を吸い上げない分、肥料過多になりやすい植物です。
栄養分(肥料分)への対策
メーカーが定める用法用量を守る
植物の成長期には、適切なタイミングで適量の肥料を与えることで、成長速度を加速させることができます。
肥料焼けのリスクを避け、植物を健康的に育てるためには、肥料メーカーが定める用法用量を守った上で使用することが重要です。
品種ごとに、望ましい肥料の量や頻度は異なるため、パッケージなどに記載されている内容をよく確認しましょう。
植物が発するサインを見逃さない
不調のサインがあらわれる前に、肥料を与えることが望まれますが、不調のサインが出てしまった場合には、すぐに肥料を与えましょう。
肥料が不足している状態から施肥を行う場合は、いきなり高い濃度で与えると、急激な変化により植物にストレスを与える可能性があります。
最初は通常よりも薄い濃度で与え、徐々に通常量に近づけるなど、急激な変化が生じにくいように、肥料を与えることが無難です。
緩効性肥料や遅効性肥料を使用する
「マグァンプ」は、植物が必要とするタイミングでのみ効き目を発揮するため、使用しやすい緩効性肥料です。
2022年の春には、肥料分だけでなく防虫機能も兼ね備えている「マグァンプD」が発売されています。
液体肥料と固形肥料の違いなどについては、以下の記事で解説しています
植物の寿命が尽きる
植物は永久的に生きられないため、寿命を迎え、その一生涯を終えるケースもあります。
植物の寿命への対策
ただし、それでも寿命に限界はあるため、いつかは還らぬ存在になるでしょう…。
咲いた花を受粉させ、採れたたねを蒔いたり、挿し木をしたり、その植物の子孫を育てることも、ひとつの対策です。
他の植物に枯らされてしまう
他の植物に巻き付いて日光を奪い取ることで、最終的に枯らしてしまうことがあるのが「締め殺しの木」という別名の由来です…。
動物界には「弱肉強食」の世界が広がっていますが、熾烈な争いが、植物界にも存在しているのです。
他の植物から栄養分を吸い上げる「寄生植物」や、他の植物の成長を抑制する「アレロパシー」を分泌する植物の存在も知られているため、自然界で起こる熾烈な争いは、めずらしいことではないのかもしれません。
元気な植物でも落葉する
植物を育てていると、時には以下のようなケースが起こることがあります。
育てている植物が葉を落とし、枯れてしまいそう…。
しかし、「植物が葉を落とす=枯れる」ということではなく、元気な植物も定期的に葉を落としています。
植物が何枚か葉を落としたとしても、焦らずに落葉した原因を探ることが重要です。
植物の「落葉」については、以下の記事で詳しく解説しています
植物を復活させる方法
元気がない原因を把握する
植物を復活させる方法は、その原因によって大きく異なります。
植物が調子を崩すのは、不調の原因が発生してから、すぐに表面にあらわれないこともあります。
場合によっては直近の2~3日ではなく、もっと以前までさかのぼってみると、正確な原因を把握できるかもしれません。
茶色くなった葉は切り落とす
枯れ込んだ葉は、そのまま付けておいても、植物にとってプラスになることはありません。
葉がウイルスに感染している場合は被害の拡大を防止でき、風通しの改善などにつながるため、剪定した方がよいです。
植え替えるのは最終手段にする
根詰まりの場合は植え替えた方がよいですが、他の原因だった場合、植え替えによるストレスが致命的なダメージを与えてしまうことにも…。
ただし、すぐに植え替えた方がよいこともあるため、判断がむずかしいですが、
植物が調子を崩したから、すぐに植え替えなきゃ!
というわけではなく、他の原因を改善してもなお調子が悪いときに、植え替えをするくらいの最終手段として捉えた方がよいでしょう。
まとめ
本記事では、観葉植物や多肉植物が枯れてしまう「11個の原因」を詳しく解説しました。
日当たり、風通し、水やりといった基本的な要素から、根詰まりや病害虫、急激な環境変化まで、枯れてしまう原因は多岐にわたります。
しかし、原因を知ることは決して悲観的なことではありません。
むしろ、大切な植物のSOSサインに気づき、適切な対策を講じるための第一歩です。
それぞれの原因に対する具体的な対策を理解し、日々の観察を通して植物の変化に耳を傾けることで、枯らすリスクを減らせます。
時には手を尽くしても、その生涯を終えてしまうこともあるかもしれません。
しかし、その経験から学び、次に迎える植物との暮らしに活かすことこそが、豊かなグリーンライフを送るための糧となるでしょう。
コメント